デイサービスの連絡帳の文例集・コメント例・季節の挨拶|廃止・存続の判断基準
介護保険法
2024/05/08
介護保険法
基本報酬
更新日:2024/05/08
【令和3年介護報酬改定】通所介護(デイサービス)で介護報酬を得るためには、加算を算定する必要があります。ここでは、デイサービスで算定できる加算・種類と算定要件・単位数についてまとめてご紹介します。事業所に合った加算を算定して、売り上げアップを目指していきましょう。
→科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
→無料研修会「24年度介護報酬改定によるマイナス影響と、生き残るために取るべき対応策」
この記事の目次
▶科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
令和3年度の介護報酬改定にて、通所介護(デイサービス)の介護報酬加算はさまざまな単位数や算定要件の変更がありました。
単位数が変更された加算に関しては、総合的に増加傾向にあります。
また、算定要件に関しては条件が緩和された加算もあり、なかには単一のものから複数の区分に分かれたものもありました。
ここでは、令和3年度の介護報酬改定で変更された、あるいは影響があった加算についてご紹介します。
▶デイサービスで加算算定業務をするなら科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド)」
個別機能訓練加算とは、利用者に機能訓練のプログラムにあわせたサービスを提供するときに算定する加算です。
令和3年度の介護報酬改定にて、既存の「個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ」は「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ」となり、個別機能訓練加算(Ⅱ)が新設されました。
個別機能訓練加算の算定のためには「個別機能訓練計画書」の作成が必要です。
看護師や理学療法士などを含めた「機能訓練指導員」が協力して利用者の評価を行い、目標の設定やリハビリを実施し、その結果の報告が求められています。
| 単位数 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:56単位/日 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ:85単位/日 個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/日 |
|---|---|
| 算定要件 | 【個別機能訓練加算(Ⅰ)イ】 ・専従の機能訓練指導員を1名以上配置 ・居宅訪問で得られた利用者のニーズと生活状況を参考に、多職種でアセスメントを行い、個別機能訓練計画書を作成する ・利用者の心身状況に応じた機能訓練の内容を設定し、機能訓練指導員が実施する ・3ヵ月に1回以上、利用者の居宅に訪問して生活状況を確認し、本人と家族に個別機能訓練計画書の進捗状況を確認し、適宜内容の見直しをする 【個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ】 ・サービス提供時間に、専従の機能訓練指導員を2名以上配置(そのうち1人以上はサービス提供時間を通じて配置) ・居宅訪問で得られた利用者のニーズと生活状況を参考に、多職種でアセスメントを行い、個別機能訓練計画書を作成する ・利用者の心身状況に応じた機能訓練の内容を設定し、機能訓練指導員が実施する ・3ヵ月に1回以上、利用者の居宅に訪問して生活状況を確認し、本人と家族に個別機能訓練計画書の進捗状況を確認し、適宜内容の見直しをする 【個別機能訓練加算(Ⅱ)】 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロのいずれかを算定している個別機能訓練計画の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けている |
参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について(2023年7月9日確認)
▶初心者でもわかる個別機能訓練加算【総論】算定要件や人員配置を解説
科学的介護推進体制加算とは、LIFE(科学的介護情報システム)に関係する新たに新設された加算です。
利用者の状態やサービスの情報をLIFEに提供し、フィードバック情報をもとにPDCAサイクルを回して介護の質を高めることを目的としています。
LIFEに提供すると、他の事業所と比較してどのような良い点・悪い点があるのか、またそれを改善するためのフィードバックが返ってきます。
| 単位数 | 40単位/月 |
|---|---|
| 算定要件 | ・利用者ごとの心身の状況をはじめとした基本情報を厚生労働省に提出している ・上記の情報、その他サービスを適切に提供するために必要な情報を活用している |
参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について(2023年7月9日確認)
▶科学的介護推進体制加算の算定要件とは?LIFEへの提出頻度や記入例
運動器機能向上加算とは、利用者に対して運動器機能向上サービスを提供するときに算定できる加算です。
要支援の利用者の身体機能の維持・向上に努め、自立して日常生活を送ることを目的としています。
理学療法士や看護師、介護職員が共同して運動器機能向上のための計画書を作成し、利用者ごとに必要なプログラムを設定・実施します。
要支援の方を対象とした加算であり、要介護の利用者に対しては「個別機能訓練加算」の対象となる点には注意しましょう。
| 単位数 | 225単位/月 |
|---|---|
| 算定要件 | ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサ ージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を持つ職員を配置した事業所で6ヵ月以上従事する必要あり)を1名以上配置する ・運動器機能向上サービスの実施にあたって、利用者ごとのリスクや体力測定などの状況を評価する ・理学療法士や看護職員などの多職種が共同して運動器機能向上計画を作成する ・運動器機能向上計画に沿ってサービスを提供する約1ヵ月ごとに利用者の目標の達成度や運動器の機能についてモニタリングし、計画の修正をする |
参考:介護保険最新情報 Vol.944(令和3年3月19日)(2023年7月9日確認)
ADL維持等加算とは、利用者のADLの機能を維持・改善しているかを評価するための加算です。
ADLをあらかじめ集計して、その後に維持・改善がみられた場合に加算が算定できます。
令和3年度の介護報酬改定では、ADL維持等加算の単位数が増加し、算定要件の緩和もみられました。
ADLを評価する指標には、バーセルインデックス(BI)が用いられています。
| 単位数 | ADL維持等加算(Ⅰ):30単位/月 ADL維持等加算(Ⅱ):60単位/月 |
|---|---|
| 算定要件 | 【ADL維持等加算(Ⅰ)】 ・評価対象利用期間が6ヵ月を超える利用者の総数が10名以上 ・利用者全員に利用開始月と、その翌月から数えて6ヵ月目にBIを測定する ・測定後と利用開始月のADL値をもとに計算して得たADL利得の平均値が1以上 【ADL維持等加算(Ⅱ)】 ・評価対象利用期間が6ヵ月を超える利用者の総数が10名以上 ・利用者全員に利用開始月と、その翌月から数えて6ヵ月目にBIを測定する ・評価した利用者のADL利得の平均値が2以上 |
参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について(2023年7月9日確認)
▶ADL維持等加算とは?算定要件をわかりやすく解説【2021年介護報酬改定】
口腔・栄養スクリーニング加算とは、口腔の健康状態と栄養状態のスクリーニングを実施することで算定される加算です。
口腔と栄養状態を定期的に確認し、利用者の健康状態の管理や症状の悪化を防ぐことを目的としています。
今までは栄養状態のみをスクリーニングする、「栄養スクリーニング加算」として取り扱っていました。
しかし、令和3年度の介護報酬改定によって、栄養スクリーニング加算が廃止され、「口腔」も含めた今回の加算に新設されました。
| 単位数 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ):20単位/回 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ):5単位/回 |
|---|---|
| 算定要件 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)は以下の両方を、(Ⅱ)はいずれか1つを満たしている (1)6ヵ月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認し、その情報を担当する (2)介護支援専門員に提供している6ヵ月ごとに利用者の利用状態について確認し、その情報を担当する介護支援専門員に提供している |
参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について(2023年7月9日確認)
なお、口腔スクリーニング・栄養スクリーニングの定義は以下の通りです。
<口腔スクリーニング>
硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者
入れ歯を使っている者
むせやすい者
<栄養スクリーニング>
BMIが18.5未満である者
直近1~6カ月間で3%以上の体重の減少が認められる者または6か月間で2~3kg以上の体重減少があった者
血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
食事摂取量が不良(75%以下)である者
口腔機能向上加算とは、利用者に対して口腔状態のケアを提供し、機能向上を図ることで算定される加算です。
今までは口腔機能向上加算に複数の区分はありませんでしたが、令和3年度の介護報酬改定では、新たに口腔機能向上加算(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれました。
口腔機能向上加算(Ⅰ)は本来の加算と同じ条件で、新たに新設された(Ⅱ)では、口腔機能を改善するための計画情報を厚生労働省に提出します。
そして、フィードバック情報をもとに、口腔機能の改善のためのPDCAサイクルの推進を目指します。
| 単位数 | 口腔機能向上加算(Ⅰ):150単位/回 口腔機能向上加算(Ⅱ):160単位/回 ※月2回まで |
|---|---|
| 算定要件 | 【口腔機能向上加算(Ⅰ)】 ・言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置する ・利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士や歯科衛生士などの多職種が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成する ・口腔機能改善管理指導計画に従って言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が口腔機能向上サービスを実施・記録する ・利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価する 【口腔機能向上加算(Ⅱ)】 ・口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定要件を満たす ・利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の情報を厚生労働省に提出し、そのフィードバック情報を活用する |
参考:令和3年度介護報酬改定について(2023年7月9日確認)
▶はじめての口腔機能向上加算|(Ⅰ)(Ⅱ)の違いや算定要件について解説
栄養アセスメント加算とは、利用者に対して管理栄養士や介護職員などが共同して、栄養アセスメントを実施したときに算定される加算です。
栄養状態の改善が必要な利用者を評価し、適切なサービスを提供できるようにすることをおもな目的として、令和3年の介護報酬改定で新設されました。
栄養アセスメント加算は、「栄養改善加算」と「口腔・栄養スクリーニング加算」と併算定ができない点には注意しましょう。
| 単位数 | 50単位/月 |
|---|---|
| 算定要件 | ・事業所の従業員または外部との連携で、管理栄養士を1名以上配置する ・利用者ごとに管理栄養士や看護職員、介護職員などの職種が共同して栄養アセスメントを実施し、その結果を利用者や家族に説明する ・利用者ごとの栄養状態の情報を厚生労働省に提出し、そのフィードバック情報を活用する ※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)および栄養改善加算との併算定はできない |
参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について(2023年7月9日確認)
栄養改善加算とは、低栄養状態またはその恐れがある利用者に対して栄養状態の改善を図る取り組みを実施したときに算定できる加算です。
栄養改善が求められる利用者を把握し、適切なサービスの提供につなげていく観点から、制度の見直しがされました。
令和3年の介護報酬改定にて、単位数が増加して算定要件にも変更がありました。
栄養改善サービスの提供にあたり、必要に応じて居宅を訪問して利用者の栄養状態を確認する条件が追加されています。
| 単位数 | 200単位/回 |
|---|---|
| 算定要件 | ・事業所内の従業者または外部との連携で、管理栄養士を1名以上配置する ・サービス利用開始時から利用者の栄養状態を把握している ・管理栄養士等と共同して、利用者ごとの食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成する ・必要に応じて利用者の自宅を訪問しつつ、栄養状態を定期的に記録する利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価する |
参考:介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(2023年7月9日確認)
参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について(2023年7月9日確認)
認知症加算とは、認知症の利用者に介護サービスを提供したときに算定できる加算です。
認知症加算を算定するには、認知症に関する研修を修了した職員の配置が必要です。
しかし、令和3年の介護報酬改定にて配置の条件が見直され、「認知症ケアに関する専門性の高い看護師」も新たに対象となりました。
利用者にも基準が設けられており、認知症によって日常生活に支障が出る方が対象となっています。具体的には、「認知症高齢者の日常生活自立度」のランクがⅢ以上の利用者が該当します。
| 単位数 | 60単位/日 |
|---|---|
| 算定要件 | ・人員基準に規定している人数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で2以上確保する ・前年度あるいは算定日の月の前3ヵ月間の利用者の総数のうち、介護を必要とする認知症の利用者が占める割合が20%以上 ・認知症介護に関する研修を修了した職員、または認知症ケアに関する専門性の高い看護師を1名以上配置する |
参考:認知症対応型共同生活介護(2023年7月9日確認)
参考:令和3年度介護報酬改定における 改定事項について(2023年7月9日確認)
若年性認知症利用者受入加算とは、若年性認知症の利用者を受け入れたうえで、担当スタッフが適切なサービスを提供したときに算定できる加算です。
対象者は40歳以上65歳未満の若年性認知症の利用者で、それぞれの特性やニーズにあわせたサービスを提供します。
加算を算定するには利用者ごとに個別の担当者を決める必要があります。
また、担当者に必要な人数や資格に指定はないので、事業所の状況にあわせて決定しましょう。
| 単位数 | 60単位/日 |
|---|---|
| 算定要件 | ・受け入れた若年性認知症の利用者ごとに個別の担当者を決める ・担当者を中心に、利用者や家族のニーズを踏まえたサービスを提供している |
参考:認知症対応型共同生活介護(2023年7月9日確認)
参考:若年性認知症対策の推進に当たっての留意事項について(2023年7月9日確認)
参考:若年性認知症(2023年7月9日確認)
延長加算とは、あらかじめ決められている基本報酬区分を超えてサービスを提供したときに算定できる加算です。
通所系サービスでは、基本報酬区分が1時間単位で設定されるようになり、その度に単位数が変動します。
また、延長加算を算定できる時間では、人員配置について特定の条件は決められていません。安全を配慮したうえで事業所の状況に適した人数配置が可能であることをおさえておきましょう。
| 単位数 | 9時間以上10時間未満:50単位/月 10時間以上11時間未満:100単位/月 11時間以上12時間未満:150単位/月 12時間以上13時間未満:200単位/月 13時間以上14時間未満:250単位/月 |
|---|---|
| 算定要件 | ・所要時間8時間以上、9時間未満のデイサービスの前後に、利用者に対してサービスを提供する ・本来の所要時間とその前後に提供したサービス時間の通算が9時間以上 |
参考:平成 27年度介護報酬改定の概要(案) (2023年月日確認)
参考:介護保険最新情報 Vol.952(令和3年3月26日)(2023年7月9日確認)
参考:介護給付費単位数等サービスコード表 Ⅰ-資料2②(2023年7月9日確認)
入浴介助加算とは、入浴中の利用者に対して介助サービスを提供した場合に算定できる加算です。
もともと入浴介助加算に区分はありませんでしたが、令和3年の介護報酬改定にて(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類に分類されました。
以前までの入浴介助加算は(Ⅰ)となり、新設された(Ⅱ)はまた別の算定要件が設けられています。
入浴介助加算(Ⅰ)の単位数は、区分されていなかった頃の加算よりも減少しました。その分入浴介助加算(Ⅱ)の単位数が多くなっています。
なお、入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できない点には注意しましょう。
| 単位数 | 入浴介助加算(Ⅰ):40単位/日 入浴介助加算(Ⅱ):55単位/日 |
|---|---|
| 算定要件 | 【入浴介助加算(Ⅰ)】 ・入浴介助を適切に行える ・人員・設備がある入浴介助を行う 【入浴介助加算(Ⅱ)】 ・入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件を含む ・医師や理学療法士、介護福祉士などが利用者の居宅を訪問して、浴室での動作や環境を評価する ・利用者の居宅の浴室が本人または家族の介助でも入浴が難しい場合は、訪問した職員と連携して福祉用具の貸与や住宅改修などの環境整備のアドバイスをする ・医師や理学療法士などとの連携のもと、利用者の身体状況や浴室環境を踏まえて入浴計画を作成する |
参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について(2023年7月9日確認)
参考:令和3年度の改定について:通所介護(2023年7月9日確認)
中重度者ケア体制加算とは、中重度の要介護者を受け入れる体制を整え、利用者に応じたサービスを提供したときに算定される加算です。
中重度者ケア体制加算を算定するには、該当する利用者が一定の割合を占めている必要があります。さらに介護職員や看護職員の人数も算定要件に含まれているので、事業所ごとに計算をする必要があります。
自治体によっては中重度者ケア体制加算を算定するための計算用のエクセルシートが用意されていることもあるので、あらかじめ検索してみましょう。
| 単位数 | 45単位/日 |
|---|---|
| 算定要件 | ・指定された基準以上の介護職員、または看護職員の数に加え、それぞれ常勤換算方法で2以上確保している ・前年度または算定月の3ヵ月間前の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者が3割以上を占めている ・サービス提供時間のなかで、専従の看護職員を1名以上配置する |
参考:平成 27年度介護報酬改定の概要(案)(2023年7月9日確認)
▶中重度者ケア体制加算とは?算定要件・単位数|職員・利用者の計算方法
サービス提供体制強化加算とは、事業所内の介護福祉士の割合や勤続年数などによって算定ができる加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、サービスの質の向上や職員のキャリアアップの推進という観点から見直しがされています。
サービス提供体制強化加算は「(Ⅰ)から(Ⅲ)」までの3種類に区分されるようになり、それぞれにあわせて単位数や算定要件が変更されています。
サービス提供体制強化加算は事業所に勤務している介護福祉士の割合や勤続年数によって区分が変わります。
| 単位数 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回(日) サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回(日) サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回(日) |
|---|---|
| 算定要件 | 【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】 以下のいずれかに該当する ・介護福祉士の割合が70%以上 ・勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上 【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】 ・介護福祉士の割合が50%以上 【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】 以下のいずれかに該当する ・介護福祉士の割合が40%以上 ・勤続7年以上の職員が30%以上 |
参考:令和3年度介護報酬改定における 改定事項について(2023年7月9日確認)
生活機能向上連携加算とは、事業所の職員と外部のリハビリ専門職が連携して、機能訓練に関するマネジメントを提供することを評価する加算です。
リハビリ専門職と連携して機能訓練を提供することで、利用者の自立支援や重症度防止を推進することがおもな目的です。
令和3年度の介護報酬改定にて、生活機能向上連携加算の内容が見直され、新たに(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類の区分に分かれました。
(Ⅰ)は新たに新設されたもので、(Ⅱ)は改定前の生活機能向上連携加算と同じ要件となっています。
| 単位数 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ):100単位/月(※3ヵ月に1回まで) 生活機能向上連携加算(Ⅱ):200単位/月(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月) |
|---|---|
| 算定要件 | 【生活機能向上連携加算(Ⅰ)】 ・外部の訪問・通所リハビリを実施している事業所またはリハビリを実施している医療提供施設のリハビリ専門職や医師からの助言を受けられる体制を作る ・リハビリ専門職や医師からの助言を受けたうえで、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成する ・リハビリ専門職や医師は、通所リハビリ等のサービスの提供の場、または通信機器によって利用者の状態を把握したうえで助言を行う 【生活機能向上連携加算(Ⅱ)】 ・外部の訪問リハビリ、通所リハビリまたはリハビリを実施している医療提供施設のリハビリ専門職や医師が事業所を訪問し、職員と共同で利用者のアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成する ・リハビリ専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3ヵ月ごとに1回以上評価して、必要に応じて計画や訓練の内容の見直しを行う ※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可 |
参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について(2023年7月9日確認)
参考:平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について(2023年7月9日確認)
▶生活機能向上連携加算とは?目的や算定要件、対象施設について
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、中山間地域等に住んでいる利用者に対して、通常の実施範囲を超えてサービスを提供するときに算定される加算です。
中山間地域等は厚生労働省が定めており、過疎地域や離島、豪雪地帯などのさまざまな地域が該当しています。
令和3年度の介護報酬改定では、介護サービスの提供を促進する観点から、対象となる介護サービスが増えました。
| 単位数 | 所定単位数の5/100 |
|---|---|
| 算定要件 | 厚生労働省が定める地域に居住する利用者に対して、通常の事業の実施地域を超えてサービスを提供する |
参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について(2023年7月9日確認)
▶中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?算定要件や単位数を解説
通所介護の減算とは、サービスの内容が不足している、運営や人員の基準が満たされていないなどの場合に基本報酬から引かれるものです。本来の介護サービスの基準を満たして、報酬を適正化することを目的としています。
それぞれの介護サービスで定められている基準を満たしていない場合、減算だけでなく指定を取り消されるケースもあるので注意しましょう。
ここでは令和3年度の介護報酬改定にて変更された、あるいは影響のあった減算についてご紹介します。
▶デイサービスで加算算定業務をするなら科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド)」
同一建物から通う場合の減算は、事業所と同じ敷地内に住んでいる利用者にサービスを提供したときの減算です。
令和3年度の介護報酬改定では、同一建物から通う場合の減算に該当した際の減算額の見直しがされています。
この制度による減算額は、通所系サービスと訪問系サービスによって違いがあります。
また、どちらも支給限度額に関しては、同一建物減算は対象外となる点には注意しましょう。
| 単位数 | −94単位/日 |
|---|---|
| 算定要件 | ・事業所と同一建物に居住する利用者、または事業所と同一建物から事業所に通う利用者にサービスを提供する ・事業所が送迎を行っていない利用者にサービスを提供する |
参考:令和3年度介護報酬改定に向けて(2023年7月9日確認)
▶同一建物等減算とは?算定要件・算定方法・単位数|注意点を解説
送迎を行わない場合の減算とは、利用者が自ら通う、あるいは家族の送迎などによって事業所が送迎を行わない場合に適用されます。
送迎減算は片道あるいは往復によって減算の単位数が異なります。
また、「同一建物から通う場合の減算」の対象となっている場合は送迎減算の対象にならない点に注意しましょう。
令和3年度の介護報酬改定にて、関連性のある「通院等乗降介助」による見直しがされましたが、送迎減算自体の変更はみられていません。
| 単位数 | 片道:−47単位/日往復:−94単位/日 |
|---|---|
| 算定要件 | 利用者に対して居宅と事業所の間の送迎を行わない場合 |
参考:令和3年度介護報酬改定における 改定事項について(2023年7月9日確認)
参考:介護給付費単位数等サービスコード表 Ⅰ-資料2④(2023年7月9日確認)
参考:15 留意事項通知(2023年7月9日確認)
▶送迎を行わない場合の減算とは?減算対象要件と単位数・送迎の考え方
定員超過利用時の減算では、月々の利用者の平均利用人数が定められている定員を超える場合に減算されます。
令和3年度の介護報酬改定では過疎地域等の介護サービスの要件について見直しがされましたが、デイサービスに関係する変化はみられていません。
災害や虐待をはじめとした事情が原因で定員超過している場合は、減算のタイミングが変化する点には注意しましょう。
事情による定員超過では、翌月からではなく、その原因が起こった月の翌々月から減算が適用されます。
| 単位数 | 所定単位数の70/100単位/月 |
|---|---|
| 算定要件 | 月々の利用者をサービス提供日数で割ったときに、平均利用人数が定められている定員数を超えている |
参考:令和3年度介護報酬改定の主な事項について(2023年7月9日確認)
参考:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2023年7月9日確認)
人員基準欠如時の減算とは、介護サービスごとに定められている人員基準を満たしていない状態でサービスを提供したときの減算です。
通所介護の人員基準欠如時の減算は、看護職員と介護職員を対象としています。人員基準欠如時の減算に該当した場合は、市区町村に届出を提出する必要があります。
届出がない、あるいは人員基準を満たしていない状態が継続すると指定を取り消される恐れもある点に注意しましょう。
| 単位数 | 所定単位数の70/100 |
|---|---|
| 算定要件 | 介護サービスの基準に定められた看護職員または介護職員を配置していない |
参考:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2023年7月9日確認)
参考:定員超過利用減算・人員基準欠如減算 – 秋田市(2023年7月9日確認)
▶通所介護の人員基準欠如減算と計算方法・人員基準違反との違い
介護報酬の加算を算定するメリットは、安定した経営の維持や質の高いサービスの提供につながることです。
反対に、減算は基本報酬から引かれるだけでなく、事業所の経営の安定性や信頼性が低下する恐れがあります。
事業所として安定しながら運営を継続するには、今回の加算・減算を理解することが重要です。
また、介護報酬改定は3年おきに変更されるため、定期的にチェックして動向を把握し、事業所の安定運営につなげていきましょう。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

介護保険法
2024/05/08

介護保険法
2024/05/08

介護保険法
2024/05/08

介護保険法
2024/05/08

介護保険法
2024/05/08
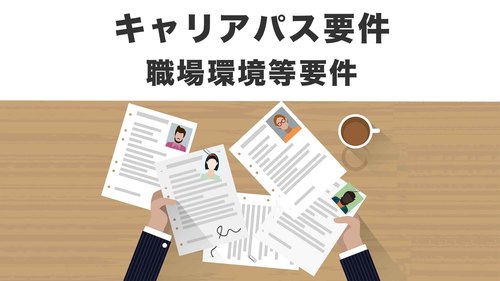
介護保険法
2024/05/08