口腔機能向上加算|運営(実地)指導に備えた自己点検シートの活用法・サービス提供手順
介護保険法
2024/05/07
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2024/04/09
【令和3年報酬改定対応】個別機能訓練加算を算定するには、利用者の居宅での生活状況を把握することが必須です。評価する用紙は生活機能チェックシートと呼ばれており、今回はシートの書き方や記入例などをご紹介します。個別機能訓練加算の概要についても解説します。
→科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
→無料研修会「24年度介護報酬改定によるマイナス影響と、生き残るために取るべき対応策」
この記事の目次
▶科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!

個別機能訓練加算は、利用者が自宅で、自立した暮らしを目指すために作られた加算です。利用者が実際に住んでいる住環境を把握する必要があるので、必ず利用者宅への訪問をしなくてはなりません。その際に必要なのが「生活機能チェックシート」です。
2021年の介護報酬改定以前は「居宅訪問チェックシート」と呼ばれており、この改定で名称が変更されました。
今回から、科学的介護の実現に向け「Barthel Index」(BI:バーセルインデックス)に沿った内容が導入され、利用者の自宅を訪問する際は、この生活機能チェックシートを活用しなければならないことを厚生労働省が定めています。
なぜなら、個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定をするには、「生活機能チェックシート」と「個別機能訓練計画書」の2点をLIFEにデータ提出する必要があるからです。
その他、生活機能チェックシートが必要な理由として、介護では看護師や理学療法士、作業療法士、医師などの他職種との情報共有が大切であるという点が挙げられるでしょう。情報共有によって、利用者の問題を掘り起こすきっかけや現状把握にも活用できます。
要介護者や病気を持つ人の日常生活動作(ADL)を評価するための指標のひとつであるバーセルインデックスについて知りたい方は、ぜひこちらの記事もご一読ください。
▶︎バーセルインデックスとは?評価項目と基準・評価する人・評価方法など
▶個別機能訓練加算を算定するなら科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド)」
個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置して、個別機能訓練を行うための計画書を作成し、それに基づいた機能訓練を実施するなどの算定要件を満たした際に算定される加算です。2021年の介護報酬改定で改訂されました。
個別機能訓練加算は個別機能訓練加算(Ⅰ)イと個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ、さらに個別機能訓練加算(Ⅱ)があります。詳細は以下の通りです。
▶個別機能訓練加算を算定するなら科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド)」
常勤や非常勤問わず、配置時間の定めはないものの、機能訓練指導員を1名以上配置する必要があります。また兼務が可能となっており、看護師が機能訓練指導員を担うことも可能です。
機能訓練指導員を2名以上配置する必要があります。また、この時1名はサービス提供時間を行う時間帯を通じて機能訓練指導員として従事しなくてはなりません。
個別機能訓練加算(Ⅱ)は、「LIFE」を活用して機能訓練に関するデータを提出することが必要です。また国からのフィードバックを活用することが算定条件となっています。
ただし、個別機能訓練加算(Ⅱ)を利用する際は、単独算定ができないことに注意してください。個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していることが必須です。
個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)の詳しい算定要件やLIFEへの提出方法については、以下の記事からチェックできますので、ぜひご一読ください。
▶︎個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの算定要件【2021年介護報酬改定】
▶︎個別機能訓練加算Ⅱの算定要件とLIFEへの提出方法

個別機能訓練加算を加算する際、利用者の居宅を訪問をする必要があります。その場合、どのようなことを確認すれば良いのか3つのポイントをご紹介します。
(1)現在している生活の状況
(2)主な生活の動線
(3)課題となっている自宅の環境
この3点を把握することで、住み慣れた環境で生活ができるように適切な福祉用具を提案したり、自宅環境を想定した日常生活の訓練を提供したりすることができるようになります。
機能訓練に活かすためのポイントとしては上記3点を中心に観察することですが、加算の算定要件として記録に残すときは少し工夫したほうがよいかもしれません。
▶個別機能訓練加算を算定するなら科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド)」
個別機能訓練加算は、効果的な機能訓練を実施するための加算です。そのため、決められた周期で利用者の状況をチェックする必要があります。そこで、必須となるのが生活機能チェックシートの活用です。
ここでは生活機能チェックシートの書き方と記入例についてご紹介します。
生活機能チェックシートで評価する際は、ADLやIADL、起居動作の各項目を 「自立」「見守り」「一部介助」「全介助」のレベルで評価します。そして、各項目に課題の有無があるかを評価するために、 「有・無」もチェックしなければなりません。
起居動作とは、人間の基本的な動作のことです。寝返りや起きあがり、座ったままその姿勢を保てるかという観点が大切です。
ADLでは日常生活動作を詳しくチェックします。普段何気なくしている起床時の動きやトイレの動作に、ふらつきや支障がないかといった観点が加わります。
IADLは、「手段的日常生活動作」を意味する言葉です。日常の動作がスムーズに行われた上で、思考や判断がともなっているかを見る項目となっています。
ADLの評価方法について知りたい方は、ぜひこちらの記事をご一読ください。
▶︎ADLの評価方法とは|介護・看護・医療で把握する目的・項目や書き方を徹底解説
ADL維持等加算ではADL評価はBIを適切に評価できる「一定の研修を受けた者」という要件が2021年の改正により追加になりました。個別機能訓練加算に必要な生活機能チェックシートでは、職種の定めはありません。
問46 個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の 者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どのような職種 を想定しているのか。また、個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問者は同一人物でなく てもよいか。さらに、居宅を訪問する者が毎回変わってしまってもよいのか。
(答) 個別機能訓練計画については、多職種共同で作成する必要がある。 このため、個別機能訓練計画作成に関わる職員であれば、職種にかかわらず計画作成 や居宅訪問を行うことができるため、機能訓練指導員以外がこれらを行っても差し支え ない。 なお、3月に1回以上、居宅を訪問し、生活状況を確認する者は、毎回必ずしも同一 人物で行う必要はない。
引用:厚生労働省「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A (平成 27 年4月1日))」
居宅訪問は、3カ月に1度行う必要があります。
居宅訪問時は、生活機能チェックシートも必要なので、同様の頻度で実施しなければなりません。ただし、毎回同じ職員が生活状況を把握する必要はなく、機能訓練指導員以外が訪問しても良いことになっています。
個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定する場合は、個別機能訓練計画書と生活機能チェックシートをLIFEへデータ提出する必要があります。この時、興味関心チェックシートは任意提出となります。また、その提出頻度は以下の通りです。
(ア)新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
(イ)個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
(ウ)アまたはイのほか、少なくとも3ヵ月に1回
アからウまでの定められている翌月 10 日までに提出することがポイントになります。また、
ということにも注意するべきです。
LIFEの概要について知りたい方は以下の記事からチェックできますので、ぜひご一読ください。
▶︎LIFE(科学的介護情報システム)とは?その目的と運用方法
生活機能チェックシートは、厚生労働省が発表している様式があるので、それを利用すると便利です。
厚生労働省の「令和3年度介護報酬改定について」から「別紙様式3-2(生活機能チェックシート)」をダウンロードできます。

個別機能訓練加算ですが、居宅訪問を行う際にも利用者に配慮した生活機能のチェックを行わなくてはいけません。ここでは、具体的に居宅訪問がどのようなトラブルに遭いやすいかをイメージするため、厚生労働省から居宅訪問に関するQ&Aが公開されているのでご紹介します。
【問42】
通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪問し、利用者の在宅生活の状況を確認した上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施することとなるが、利用者の中には自宅に人を入れることを極端に拒否する場合もある。入れてもらえたとしても、玄関先のみであったり、集合住宅の共用部分のみであったりということもある。このような場合に、個別機能訓練加算を取るためにはどのような対応が必要となるのか。【回答】
利用者の居宅を訪問する新たな要件の追加については、利用者の居宅における生活状況を確認し、個別機能訓練計画に反映させることを目的としている。このため、利用者やその家族等との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、通所介護事業所の従業者におかれては、居宅訪問の趣旨を利用者及びその家族等に対して十分に説明し、趣旨をご理解していただく必要がある。
【問43】利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に居宅訪問を行い利用者の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場合、個別機能訓練加算の算定要件を満たすことになるか。
【回答】利用契約前に居宅訪問を行った場合についても、個別機能訓練加算の居宅訪問の要件を満たすこととなる。【問45】居宅を訪問するのは、利用者宅へ送迎をした後そのまま職員が残り、生活状況を確認することでも認められるか。
【回答】認められる。
【問46】
個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どんな職種を想定しているのか。また、個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問者は同一人物でなくてもよいか。さらに、居宅を訪問する者が毎回変わってしまってもよいのか。【回答】
個別機能訓練計画については、多職種共同で作成する必要がある。このため、個別機能訓練計画作成に関わる職員であれば、職種に関わらず計画作成や居宅訪問を行うことができるため、機能訓練指導員以外がこれらを行っても差し支えない。なお、3月に1回以上、居宅を訪問し、生活状況を確認する者は、毎回必ずしも同一人物で行う必要はない。
興味関心チェックシートは、通所介護で個別機能訓練加算を算定する際に、利用者の日常生活や社会生活等について、現在行っていることや今後行いたいこと(ニーズ・日常生活や社会生活等における役割)を把握するために活用することと示されたシートです。
項目は、日常生活や家事動作・趣味・スポーツ・社会参加などで、利用者が実際に「している」「してみたい」「興味がある」の3つで評価します。下記記入例のように該当する箇所に「○」を付けるだけです。
趣味や社会参加への目標は、なかなか聞き出せない情報です。利用者の趣味嗜好や社会参加への意欲などを新たに探り、介護現場での機能訓練に活用してください。
ご本人からお聞きできない場合は、ご家族に元々好んでいた趣味などをお聞きするのも良いでしょう。
「興味関心チェックシートの様式」のお役立ち資料(PDF)を無料プレゼント中ですので、必要な方はダウンロードしてください。
また、興味・関心チェックシートに関する詳しい内容や記入方法は、以下の記事で解説しています。
▶興味・関心チェックシートとは?活用方法と記入例【様式ダウンロードあり】
日常生活における生活機能の維持・向上を目指す機能訓練を行うためには、その利用者のADLやIADLに配慮した内容でなければなりません。寝たきりの方にいきなり歩行を進めるような機能訓練にならないように、利用者の特性をしっかりと見る必要があります。
生活機能チェックシートは「居宅での生活を維持する」という前提のために作られたものです。だからこそ、居宅訪問を行い、環境や利用者の生活レベルがどのようなものかを把握する必要があるのです。
生活機能チェックシートを活用することで、個別機能訓練加算も算定できます。利用者のさらなる機能訓練を目指し、ぜひ活用したい加算です。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

介護保険法
2024/05/07

介護保険法
2024/05/07

介護保険法
2024/05/07

介護保険法
2024/05/07
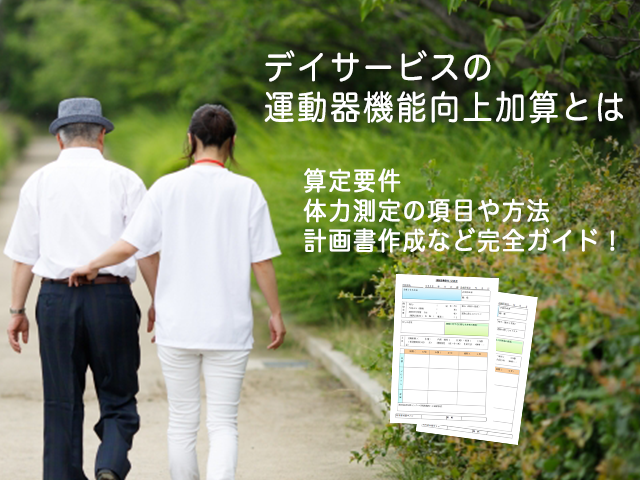
介護保険法
2024/05/07

介護保険法
2024/05/07