廃用症候群(生活不活発病)とは|原因・症状・リハビリについて専門家が解説
機能訓練
2024/04/26
機能訓練
その他
更新日:2024/04/07
デイサービスでのリハビリ体操をご高齢者の身体状況に合わせ提案することは非常に大変な作業です。しかし、リハビリ体操がマンネリ化したままでは興味や関心、楽しみも生まれません。目的がわからないまま高齢者の方に運動を提案するのではなく、効果と目的を明確にして高齢者にお伝えすることがリハビリ体操のポイントになります。
この記事の目次

デイサービスで行うリハビリ体操は、高齢者が要介護状態になることを予防(一次予防)することや状態悪化を予防(2次予防)することを目的として行います。これらを総じて介護予防を目的とした健康体操のことを一般的に「リハビリ体操」といいます。
地域の取り組みを見てみると介護予防と自立支援を目的にした「地域リハビリテーション支援体制整備推進事業」が様々な自治体でインストラクターの指導のもとリハビリ体操を実施されています。リハビリ体操のインストラクターには「介護予防運動指導員」や「介護予防指導士」など様々な民間資格があります。主に高齢者筋力向上プログラム、トレーニングの指導、効果測定(評価)など介護予防に必要な実践プログラムを開催しています。
このように高齢社会の今、いかに健康寿命を延伸していくのかが日本の課題であり、それに取り組まれている皆様は日本の未来を背負って立つ仕事をされているのです!
集団体操やレクリエーションのプログラムを知りたい方は、ぜひこちらの記事をご一読ください。
▶︎デイサービス体操 全21種|高齢者が椅子に座ってできる運動方法のご紹介

では実際に介護現場でリハビリ体操どのように取り組まれているかについて考えていきましょう。
デイサービスをご利用されているご高齢者の方々にとって、リハビリ体操はやらなければならないけれどもなかなか続かないものです。ましてや加齢や持病により身体的に疲労感があるご高齢者は、日々運動に取り組むことに苦痛を感じてしまうことも多くあるのでしょう。ここで効果も説明もなく、いつもと同じようなマンネリ化した運動を提案されてしまってはモチベーションが上がらないのも当然なのではないでしょうか?
日頃の運動や健康体操にやる気を引き出し、モチベーションを維持していくためには「目的のある運動」を常に提供し続ける必要があります。
一方、高齢者の方々は新しいことを覚えるのが苦手でもあり、パターン化された運動を提供することも必要です。ある程度慣れてきて、体に徐々に力が付いてきた段階で、次のステップに進めるような段階的なトレーニングを提案できることが、非常に素晴らしいリハビリ体操の提案ではないでしょうか!

今回ご紹介するリハビリ体操では、「簡単」「場所を取らない」「お手軽」といったテーマで、デイサービスでも簡単に用意できる道具別の運動方法のご紹介をします。
【デイサービスで準備がしやすい道具】
セラバンドなどは金額も安く手に入りやすいリハビリ道具ですので、是非この機会に購入してみてはいかがでしょうか。

こちらの運動はセラバンドを活用したふくらはぎのリハビリ体操です。ふくらはぎは歩く時に地面を蹴って前方への推進力を促したり、前方へのバランスを保つ場合に働きます。高齢者の筋力トレーニングとして取り組んではいかがでしょうか。
セラバンドは、リハビリ病院やデイサービスなどでもリハビリ体操の道具で、バンドの色によって強度を選択することができます。また、バンドの長さを調節したり、二重にしたりすることでも強度を調整できる便利な道具です。
【回数】
10回を目安に行いましょう。
下半身の引き締めや筋力アップに効果が期待できるセラバンドを活用したトレーニングについて知りたい方は、ぜひこちらの記事をご一読ください。
▶︎セラバンドの筋トレ特集|下半身の効果的な鍛え方【12選】


こちらはゴルフボールを活用した足の裏のマッサージのリハビリ体操です。
足裏には足底腱膜や母趾球筋、小趾球筋と言われる筋肉・腱膜が存在します。ボールを使用してこれらの筋肉をマッサージしていくことができます。高齢者の方になると足裏の柔軟性が落ち、指先が固まってしまうためバランスを保つことが苦手になってしまいます。しっかりとゴロゴロしていただきましょう。
【回数】
10回を目安に行いましょう。

DYJOC(ディジョック)というビー玉を使用した足指の巧緻動作のリハビリをご紹介します。
足の指や腹で挟む動作を鍛えることで、足の指の機能や空間での操作を学習することができます。高齢者の転倒予防には臀部の筋力増強やバランス訓練など様々な要因がありますが、足の指の機能を賦活することも足の指・足関節で姿勢を制御する働きとして転倒予防に効果が期待できます。人間はロボットのように歩いているわけではなく、足先などで重心をコントロールする力があります。高齢者になるとどうしても足先が硬くなり、動きが悪くなってしまいます。そのため高齢者の方の転倒予防エクササイズの1つとして取り入れてみてはいかがでしょうか。
【回数】
10個を目安に行いましょう。

こちらのリハビリ体操は「タオルギャザー」という足の指や足関節を使用した運動です。
ビー玉の体操と同様に指先の筋力や巧緻動作に加え、足首の運動も行うことができます。この運動を行うことによりご高齢者においては、歩行中のつま先が引っかかるような転倒予防に効果が期待できます。ご利用者様の能力に応じてタオルの先に重錘やダンベルなどの重りを置くのも良いでしょう。
【回数】
足の指でタオルを全て巻き取ります。
「タオル」を使用した太もものリハビリ体操をしよう!

こちらのリハビリ体操は、膝の下にタオルを設置して膝の曲げ伸ばしを行う太もも(大腿四頭筋)の筋力トレーニングです。ご高齢者は加齢に伴い特に太ももの筋力が低下しやすいと言われています。太ももの筋力が低下することで、膝の関節が不安定となり痛みを伴ったり、膝折れやふらつきやすくなります。転倒予防や膝痛予防として徹底して太ももの筋力をアップしておきましょう!!
【回数】
10回×3セットを目安に行いましょう。

こちらのリハビリ体操は、棒を活用した上半身と体幹のストレッチです。
ご高齢者の中で円背や猫背の方はいらっしゃいませんか。この姿勢を長時間続けていると胸郭が狭くなるため呼吸機能が低下しやすくなります。棒体操に取り組み、胸や脇腹の柔軟性を高めておきましょう!棒体操は新聞を丸めて棒にするなど準備がしやすく、どなたでも取り組みやすい運動です。デイサービスや介護施設でも取り入れてみてはいかがでしょうか。
【回数】
左右共に10回ずつを目安に行いましょう。

棒を活用したリハビリ体操の魅力を一つご紹介します。
こちらのリハビリ体操は、棒を背中の後ろで上下運動をすることで入浴時の洗体動作や更衣動作の下衣動作の引き上げなどの模倣練習として活用できます。リハビリ体操をご利用者様に運動を提案する場合は「この運動は背中が洗いにくい方の肩の柔軟性を改善します」と目的をしっかりと説明してあげることで納得のいくリハビリ体操が行えます。
相手に納得していただける具体的な目的を伝えて、リハビリ体操を実施していく。これがリハビリ体操の基本的原則です!
【回数】
上下に20回を目安に行いましょう。


こちらのリハビリ体操は、ペットボトルを使用した体幹筋を鍛えるエクササイズです。体幹筋とは、手足と顔を除く部分で主に胴体部分を示します。この筋力が弱まることで、体の軌道修正が効かず体がすぐに後方に倒れたり、つまずいても正常の位置に体を戻すことができにくい体になってしまいます。そこで体幹を鍛えて、体の軸を安定させていきましょう。
ご高齢者には徹底して体幹の筋力をつけて「貯筋」しましょう!
【回数】
左右交互に20回を目安に行いましょう。


こちらのリハビリ体操は、転倒予防やバランス保持のために必要な「バランス能力」を鍛えるトレーニングです。
転倒予防には、筋力をアップだけでなく必ずバランス訓練が必要です。筋力と転倒は相関関係があるだけです。ご高齢者の転倒予防のためには、これまで紹介した体操に合わせてバランス訓練をしていくことをお勧めします。
デイサービス・機能訓練指導員が活用できる「リハビリ体操・運動」関連の記事を一挙にまとめました。状況に合わせてうまく活用していただけたら嬉しく思います。記事が増えていけば随時更新していきます。
→→ 【完全保存版】デイサービス・機能訓練指導員が活用できる高齢者のためのリハビリ体操・運動まとめ|随時更新
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

機能訓練
2024/04/26

機能訓練
2024/04/26
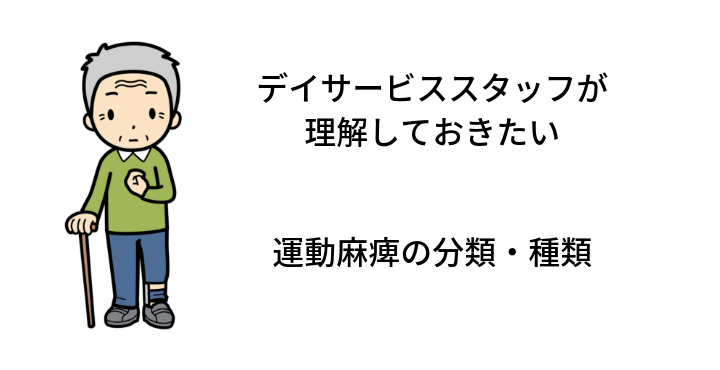
機能訓練
2024/04/26

機能訓練
コラム
2024/04/11

機能訓練
2024/04/10

機能訓練
2024/04/10