廃用症候群(生活不活発病)とは|原因・症状・リハビリについて専門家が解説
機能訓練
2024/04/26
機能訓練
下肢
更新日:2024/04/01
機能訓練プログラムでお悩みはありませんか?今回は、デイサービスで行う機能訓練の中でも「排泄動作」に着目して、機能訓練計画書の目標の立て方、目標例、訓練内容・メニューについて事例を通してご紹介していきます。
▶︎令和6年度の介護報酬改定では、科学的介護の推進がさらに加速します。LIFEの利用も必須になっていくことが予想されます。スムーズにLIFEに情報を提出されている各地の事業所の事例をご紹介します。

排泄動作訓練を考える時は、「排泄」そのものについて考える必要があります。排泄とは、不要になった老廃物を体外に排出する命をつなぐための人間の生理的な行為です。そして排泄動作とは、この行為を遂行するための移動動作や上肢操作など全般を指しています。排泄動作を大きな要素で分解してみると、以下のようになります。
【排泄動作の要素】
これらの要素の中で一人では困難な動作が「要介助」であり、全てにおいて自立して行える場合を「自立」と判断します。
機能訓練のプログラムを考える上では、上記の要素を分解して、要素の一つ一つに対して「どうしてできないんだろう?」を分析することが重要です。これを「評価」と呼び、それらに基づいた改善策がプログラム内容となります。
利用者が排泄自体を行う前に、「尿意や便意を感じることができる」か否かを確認することも重要です。もし困難な場合は、失禁するケースが多くみられますので、注意する必要があるでしょう。

機能訓練の目標を立てる際は、日常生活動作や家事動作、趣味活動、社会参加などの多くの視点や活動の手順を理解して段階的に関わることが求められます。デイサービスでは利用者の居宅訪問などで生活状況を把握して、排泄動作のどこに課題があるのかを確認します。その課題を計画書の目標に設定していきますが、ここでは例をご紹介します。
【排泄動作の目標例】
【トイレの介助が必要な動作】
個別機能訓練計画書の短期目標の立て方は、目標とする「排泄動作の自立」を達成するために必要な工程(現在、介助を要している動作)を目標として立案します。
次に、この短期目標を獲得するために必要な工程をプログラム(機能訓練や模倣訓練)として立案していきます。
【機能訓練プログラム】
●短期目標:便座・車椅子からの立ち上がりを安定して行えるようになる(見守り)
→プログラム①|集団体操
→プログラム②|立ち上がり訓練
●短期目標:便座・車椅子への移乗が安定して行えるようになる(見守り)
→プログラム③|立位バランス訓練
●短期目標:ズボンの着脱が自立して行えるようになる(見守り)
→プログラム④|ズボン着脱訓練
→プログラム⑤|トイレ動作訓練
「排泄動作の自立」には5つのプログラムが必要となり、このプログラムを実施することで短期目標の達成を目指していきます。
それでは、ここからは立案したプログラムに沿って機能訓練の内容をご紹介していきます。

ポータブルトイレの自立を獲得したい場合には、まず「集団体操」を提案します。
これまでに運動習慣がない場合は、いきなり筋力トレーニングや立ち上がり訓練、トイレ動作訓練をすることは障壁が高くなるため、工夫が必要です。
そういった場合は他者との交流を持ちながら簡単な運動ができるよう、午前中に20分間開催しているデイサービスの集団体操から促すなど、軽い運動から進めていきます。
【訓練内容】
【期待する効果】



排泄動作の中でも「立ち上がり」に課題がある場合、立ち上がりを獲得するためには、太ももや体幹筋の筋力アップが必要です。
こちらの運動は、椅子からの立ち上がりに必要なふくらはぎと太もも、体幹筋を鍛える運動メニューです。この3つの運動を定期的に取り組むことで立ち上がりに必要な筋力と反復的な動作学習を促すことができます。立ち上がりが不安定な間は、手すりを持ったりスタッフの介助を行うようにしましょう。
【訓練内容】
【期待する効果】


次に「立位のバランス」に課題があり、特に後ろに振り向いたり、その場で方向転換をする場合にふらつきが目立ったりする場合、主に反復動作によってバランスが安定するように上図のような機能訓練を実施していきます。
こちらの運動は、立位のバランスに必要な体幹の捻り動作と足踏み動作です。こちらもバランスが不安定な間は、手すりを持ったりスタッフが少し支えてあげるようにします。
【訓練内容】
【期待する効果】


「ズボンの着脱」に課題がある場合は、上図のように改めてズボンの着脱の手順を一つ一つ確認しながら訓練を実施するなど、利用者の状態に合わせて着脱の動作を少しずつ進めていきます。
こちらの運動は、トイレでのズボンの着脱を想定した「座位」と「立位」でのズボンの着脱訓練です。ズボンの着脱は座ってもできる動作なので、まずは椅子に座ったまま着脱の練習をします。
【訓練内容】
【期待する効果】
座位、立位でのバランス能力の向上

ここからは、排泄動作の実践的なプログラムになります。
今までの4つの機能訓練に取り組んで立ち上がりや方向転換、ズボンの着脱ができるようになった場合は、「実際にトイレに行って練習してみませんか?」と提案します。
身体機能がアップしていれば、実際のトイレではスムーズに動作ができるようになっていきます。
【訓練内容】
【期待する効果】
ここまでくれば見守りでトイレ動作ができるようになり、個別機能訓練の成果がはっきりと表れてきます。
排泄に関する機能訓練メニューを紹介しました。さまざまな病気や怪我を抱えている利用者に対し、安全で適切な訓練メニューを考えるのは一苦労です。
日常動作のひとつである「排泄」をよりスムーズにするために、紹介した機能訓練をぜひ活用してください。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

機能訓練
2024/04/26

機能訓練
2024/04/26
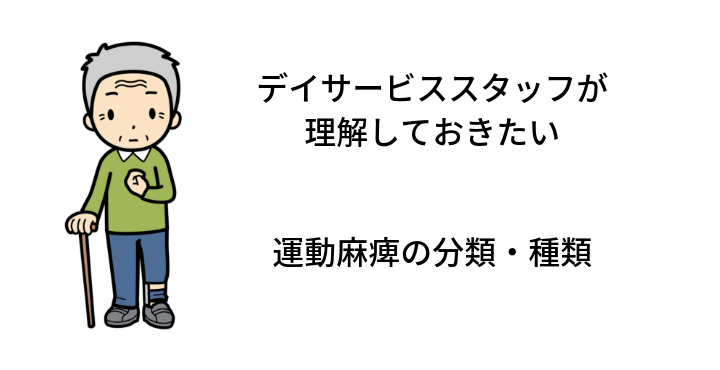
機能訓練
2024/04/26

機能訓練
コラム
2024/04/11

機能訓練
2024/04/10

機能訓練
2024/04/10