2024年4月までに策定が義務化!業務継続計画(BCP)策定方法をゼロから丁寧に解説【セミナーレポート】
運営ノウハウ
2024/04/26
運営ノウハウ
運営
更新日:2024/04/01
介護と腰痛は切っても切れない関係性にあります。というのも、介護スタッフの腰痛率は「約6割」と言われており、介護離職・退職の原因の1つとなっています。人手不足と言われている介護業界。スタッフの退職は経営者の方からみたら避けたいものです。そこで今回の記事では、介護と腰痛にフォーカスをあてて原因・予防・対策方法についてご紹介していきます。
この記事の目次

厚生労働省(平成 21 年)によると業務上疾病の発生件数は 7,491 件となっており、そのうち「腰痛」は 4,870 件(非災害性含む)と 60%以上を占めています。
業種別の腰痛発生割合をみてみると、介護業務を含む「保健衛生業」は全体の約24%を占める結果となっており年々増加傾向にあります。
対象・動作別の発生割合では、「人」が 83.5%を占めています。
つまり、ご利用者様の介助や多くの方と接する介護現場では「腰痛」に悩む方が多いと考えられます。「人」とは、 人を介助する、取り扱うなどの人が介在する動作のことを示しています。
介護スタッフの腰痛発生割合が高いことは説明しましたが、介護職員の方は比較的年齢層が高いということもありますが、腰痛が退職の原因の1つと言われています。
腰痛は労働生産性にも大きく影響してきますので、介護スタッフの腰痛予防や対策は急務といっても大げさではありません。早めの対処をしていきましょう。

どの経験年数のスタッフが、職場での腰痛になりやすいのでしょうか。
年配の方をイメージした方も多いのではないでしょうか。経験年数別の腰痛発生割合は、「1~3 年未満」が25.7%と最も多くなっており、次いで「1 年未満」が 24.5%となっています。
つまり、介助方法や関わり方に慣れていない経験年数1〜3年目のスタッフ(全体の50%以上)の多くが腰痛に悩まされていることが分かります。

腰痛の発生に関連する要因として、 以下の4つが挙げられます。
→ 中央労働災害防止協会「介護事業・運送事業における腰痛予防テキスト作成委員会」

介護現場でよくある2つの場面を想定して介助のポイントを抑えておきましょう。
※添付資料に厚生労働省の「腰痛予防対策チェックリスト」を添付しておりますので、ご興味のある方はチェックしてみてください。

職場の仕事の合間、休憩時間に行うことを想定した腰のストレッチをご紹介します。
筋肉に張りや凝りなどの違和感を感じた時に行いましょう。また、筋肉に違和感がない場合でも休憩時間などに随時行い、腰痛予防をすることをオススメします。筋肉の張りや凝りは、まとめてやるのではなく、その日のうちに解消するのが一番です。

太ももの裏に付着する「ハムストリングス」をストレッチしていきます。
このハムストリングスはお尻の付け根まで付着するため、骨盤の動きと連動しています。腰を直接ストレッチするだけでなく、こちらも行っていきましょう。
運動初心者からスポーツをされている方まで取り組める姿勢別のハムストリングスのストレッチについて知りたい方は、ぜひこちらの記事をご一読ください。
▶︎姿勢別のハムストリングスストレッチ 全18種について

腰部を守っているのは「腰」と「お腹」の筋肉と靭帯です。
特に腹筋の力が低下すると、腰椎の前彎が強くなり腰に負担がかかりやすくなります。その為、腹筋を鍛えて腰にかかる負担を支えるサポートをしておきましょう!
すでに、腰痛をお持ちの方はコルセットを使用することも手立ての一つです。
介護業務においては、長時間の中腰姿勢や介助により、腰に過重な負担のかかる作業が多くあります。
そのため、中央労働災害防止協会(平成22年)では「介護事業・運送事業における腰痛予防テキスト作成委員会」を設け、施設介護および訪問介護業務の従事者の方を対象にテキストも作成しているようです。詳しくご覧になりたい方は、そちらも参考にしてみてください。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

運営ノウハウ
2024/04/26

運営ノウハウ
2024/04/26

運営ノウハウ
2024/04/26

運営ノウハウ
2024/04/26
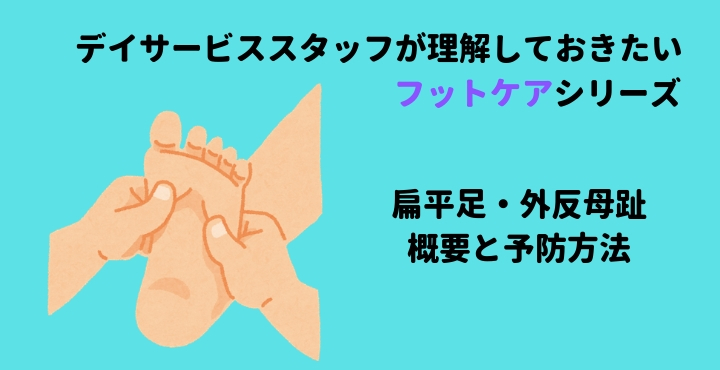
運営ノウハウ
2024/04/26

運営ノウハウ
2024/04/25