介護のアセスメントとは?目的や重要性・書き方のコツやポイントを紹介
コラム
2024/04/19
コラム
介護スタッフの基礎知識
更新日:2024/03/21
デイサービスのアセスメントシートとは、介護サービスの利用者がサービスを利用することになった背景や心身の状態、必要な支援の内容など基本情報をわかりやすくまとめたシートです。 ケアプラン作成や利用者の課題把握のために欠かせない書類です。ここでは、アセスメントシートの役割や目的、様式などをご紹介していきます。
→科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
→無料研修会「ついに始まる2024年度介護報酬改定 全貌を一気に解説!」
この記事の目次
通所介護の運営基準では「通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されなければならない」と定められています。そのため、デイサービス利用者の情報をヒアリングする「アセスメント」が必要です。
利用者の生活動作や認知症の有無、家族の状況などを整理してまとめた書類をアセスメントシートと呼び、通所介護計画作成に役立てられています。
この記事で解説しているアセスメントシートとは、「通所介護計画作成のためのアセスメントを記録したもの」を指します。
通所介護の担当者は、個別機能訓練加算や口腔機能向上加算など、加算算定のために適宜アセスメントを行います。その場合も「アセスメントシート」と呼ぶことがあるため、認識がずれないよう注意が必要です。
上記の図のように、なんのためのアセスメントなのかをしっかりと確認しておき、各施設でのシートの呼び方(フェイスシート、利用者台帳、顧客管理台帳など)を頭に入れておきましょう。
通所介護では、すべての利用者に対してアセスメントを実施し、通所介護計画書を作成することが義務付けられています。アセスメントと通所介護計画書は連動しているものなので、通所介護計画書を作成・更新するたびにアセスメントが必要になります。
利用者や家族の要望や現状の様子を把握するために、アセスメントシートは欠かせないものなのです。
以下の記事を参考にして、通所介護計画書についても理解を深めておきましょう。
▶通所介護計画書の作り方とは?手順や記入例・様式・更新期間などを解説
アセスメントシートには厚生労働省が指定する様式がありません。各事業所で独自に管理されており、主に利用されているのは介護ソフトやExcelを利用した独自のシートです。
他の事業形態や介護支援専門員など向けに開発されたアセスメント方法には以下のようなものがあります。
ここではケアマネジャーに向けて、基本情報9項目と課題分析に関する14項目から、参考として23項目を課題分析標準項目を紹介します。ただ、この項目だけを取り込めば利用者の情報が全て把握できるわけではありません。ライフスタイルや趣味など、利用者と家族が目指す生活などを広く探っていく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本情報(受付、利用者等基本情報) | 居宅サービス計画作成についての利用者受付情報(受付日時、受付対応者、受付方法等)、利用者の基本情報(氏名、性別、生年月日、住所・電話番号等の連絡先)、利用者以外の家族等の基本情報について記載する項目 |
| 生活状況 | 利用者の現在の生活状況、生活歴等について記載する項目 |
| 利用者の被保険者情報 | 利用者の被保険者情報(介護保険、医療保険、生活保護、身体障害者手帳の有無等)について記載する項目 |
| 現在利用しているサービスの状況 | 介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けているサービスの状況について記載する項目 |
| 障害老人の日常生活自立度 | 障害老人の日常生活自立度について記載する項目 |
| 認知症である老人の日常生活自立度 | 認知症である老人の日常生活自立度について記載する項目 |
| 主訴 | 利用者及びその家族の主訴や要望について記載する項目 |
| 認定情報 | 利用者の認定結果(要介護状態区分、審査会の意見、支給限度額等)について記載する項目 |
| 課題分析(アセスメント)理由 | 当該課題分析(アセスメント)の理由(初回、定期、退院退所時等)について記載する項目 |
| 健康状態 | 利用者の健康状態(既往歴、主傷病、症状、痛み等)について記載する項目 |
| ADL | ADL(寝返り、起きあがり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等)に関する項目 |
| IADL | IADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)に関する項目 |
| 認知 | 日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関する項目 |
| コミュニケーション能力 | 意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーションに関する項目 |
| 社会との関わり | 社会との関わり(社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等)に関する項目 |
| 排尿・排便 | 失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度などに関する項目 |
| じょく瘡・皮膚の問題 | じょく瘡の程度、皮膚の清潔状況等に関する項目 |
| 口腔衛生 | 歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目 |
| 食事摂取 | 食事摂取(栄養、食事回数、水分量等)に関する項目 |
| 問題行動 | 問題行動(暴言暴行、徘徊、介護の抵抗、収集癖、火の不始末、不潔行為、異食行動等)に関する項目 |
| 介護力 | 利用者の介護力(介護者の有無、介護者の介護意思、介護負担、主な介護者に関する情報等)に関する項目 |
| 居住環境 | 住宅改修の必要性、危険個所等の現在の居住環境について記載する項目 |
| 特別な状況 | 特別な状況(虐待、ターミナルケア等)に関する項目 |
参照:「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示に ついて」の一部改正等について (介護保険最新情報Vol.958等の再周知)
通所介護計画書を作成する際、ケアプランが作成されている場合は、その内容も加味して作成するのが一般的です。しかし、ケアプランのみの情報だと、通所介護のアセスメント結果としては不十分になり、上図のように利用者のニーズに応えられない場合もあります。
適切な介護を提供するためには、通所介護の利用開始時だけでなく、通所介護計画書の更新や変更があるたびにアセスメントシートを作成するのが大切です。アセスメントで得た情報があるからこそ、相応の介護サービスを通所介護計画書をもって提供できる、ということです。
運営(実地)指導で指摘される場合もありますから、アセスメントのタイミングや頻度については十分注意しておきましょう。
ケアプランについては以下の記事が参考になります。ケアプランと通所介護計画書の違いについてもしっかり認識しておきましょう。
アセスメントシートは利用者を深く理解し、記録するための大切なツールです。通所介護計画書はアセスメントシートを基本にして作られていることが前提ですから、アセスメントの段階で利用者の課題をしっかりつかんでおかなければなりません。
利用者の趣味や生活スタイル、家族の要望など多くのことに触れるために作成されるのがアセスメントシートであり、利用者と家族を理解するための第一歩と位置づけておくとよいでしょう。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

コラム
2024/04/19

コラム
2024/04/18

コラム
2024/04/18

コラム
2024/04/18

コラム
2024/04/18
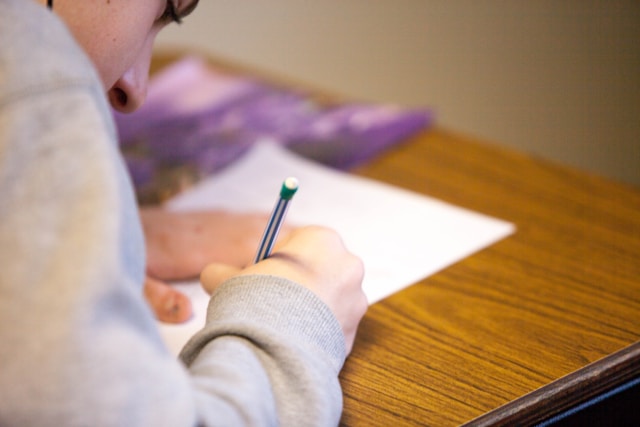
コラム
2024/04/17