介護のアセスメントとは?目的や重要性・書き方のコツやポイントを紹介
コラム
2024/04/19
コラム
介護スタッフの基礎知識
更新日:2023/07/24
お泊まりデイサービスとは、日中デイサービスを利用している方が、夜もそのまま施設に宿泊できるサービスです。このサービスは、個人契約を締結する保険外のサービス形態です。この記事では、お泊まりデイサービスの運営指針や課題や規制、気になる疑問などについて解説します。
→科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
→無料研修会「ついに始まる2024年度介護報酬改定 全貌を一気に解説!」
この記事の目次
お泊りデイサービス とは、昼間にデイサービスを利用し、そのまま夜間も引き続き宿泊できる介護保険外サービスです。
介護保険における宿泊サービスは、いつでも簡単に利用できる訳ではありません。介護保険サービスにおいて、以下のような状況が問題になり得ます。
上記の理由によって、宿泊サービスの利用は難しい状況が考えられます。
お泊りデイサービスでは、日中利用しているデイサービス施設に宿泊するため、心理的な負担が少なく安心して宿泊できます。慣れた施設やスタッフなどの環境が利用者の不安感を軽減する要素になるでしょう。
また、お泊まりデイサービスは、保険点数を気にせずに使用できるというメリットがあります。
介護保険を利用する場合、要介護度に応じた支給限度額が定められており、支給限度額の範囲内に収めなければなりませんが、介護保険外サービスであれば支給限度額を気にせずに利用できます。
一方、お泊まりデイサービスは介護保険外サービスのため、行政が定めた基準がなく、以下のような問題点が指摘されていました。
しかし、平成27年に厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」という通知が発行され、一定の指針をもとに利用者がより安心して利用できる環境になりました。
次章より、お泊まりデイサービスの運営基準や関連する制度についてご紹介して行きます。
介護保険外サービスについて知りたい方は以下の記事からチェックできますので、ぜひご一読ください。
在宅生活を送っている利用者が一時的に宿泊することを希望した場合、最も一般的に利用されるのはショートステイです。
ショートステイは介護を必要とする方が一時的に施設に滞在し、必要なケアやサポートを受けられる介護保険サービスです。
お泊まりデイサービスとショートステイは、どちらも短期間の宿泊を提供する介護サービスとなりますが、異なる点がいくつかあります。以下に相違点をまとめましたのでご参考ください。
| お泊まりデイサービス | ショートステイ | |
|---|---|---|
| 介護保険の適用有無 |
介護保険適用不可全額自己負担 |
介護保険適用(1〜3割負担) |
| 対象者 |
特に条件はない ※厚生労働省の指針は次のように示されている(宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況により、若しくは利用者の家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象) |
要介護認定を受けている方
|
| 人員 |
介護職員または看護職員1人以上(食事の提供を行う場合は、食事の介助などに必要な人数) |
|
| サービス |
|
|
| 利用までの流れ |
|
|
参照:厚生労働省 短期入所生活介護(ショートステイ)
参照 :指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について
参照 :厚生労働省 社保審-介護給付費分科会 短期入所生活介護
参照 :通所介護事業所の設備を利用した介護保険制度外の宿泊サービスの提供実態等に関する調査研究事業報告書(平成28年3月三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
このように、類似するお泊まりデイサービスとショートステイですが、それぞれ異なる特徴を持ちます。
施設や地域によって具体的な提供内容が異なる場合もありますので、詳細な情報はお近くの施設や地方自治体へご確認ください。
厚生労働省からガイドラインが発出される以前、お泊まりデイサービスは介護保険外サービスのため行政が定めた基準がありませんでした。宿泊場所や人員などの基準が決まっておらず、問題視されていました。
そこで、平成27年にお泊まりデイサービスの環境を整えることを目的に厚生労働省により一定の運営基準が定められました。その後、指針をもとに利用者がより安心して利用できる環境へと変化しつつあります。
お泊まりデイサービスの運営指針について、3項目にまとめましたのでご参考ください。
| 職員配置基準 |
宿泊時間帯には、介護職員または看護職員の1人以上の常駐 |
|---|---|
| 利用定員基準 |
利用定員は、日中のデイサービスの利用定員の半分以下、最大でも9人まで。 利用者の希望等により処遇上必要と認められる場合を除き、男女が同室で宿泊することがないように配慮する。 |
| 利用定員 |
|
|---|---|
| 床面積 |
宿泊室は1部屋あたり最低7.43㎡(四畳半)以上の広さが確保される。相部屋の場合は、7.43㎡に相部屋利用者の数を乗じた面積以上の広さが必要。 |
| 就寝準備・起床援助 |
|
|
食事の提供 |
|
| 排泄援助 |
|
| 入浴 |
指針には示されていない。 |
| 消防法の遵守 |
消防法によって定められているスプリンクラーや火災報知器、消防器などの防火設備を確実に設置していなければならない。 |
|---|---|
| 防災対策 |
|
| 緊急対応 |
|
参照:指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について 平成27年4月厚生労働省
参照:「千葉県における指定通所介護事業所の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外の サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン」令和3年9月 千葉県
参照:「千葉県における指定通所介護事業所の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン」及びその届出について 令和3年10月 千葉県
参照:厚労省通知vol.470「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」(平成29年6月4日アクセス)
お泊まりデイサービスは原則的に緊急時または短期的な利用を想定しています。ただし、厚生労働省からの指針では、宿泊期間について明確なガイドライン規定は定められていません。
長期滞在や連泊についてはデイサービス事業所に判断が任されています。しかし、長期滞在や連泊が常習的になることで、そのデイサービスが入所施設化することが問題視されているのも事実です。
お泊まりデイサービスを利用するにあたって、自治体によっては利用可能日数の上限が設定されている場合もあるため、確認する必要があるでしょう。
たとえば、千葉県・埼玉県・愛知県・広島県・大阪市などでは「利用者に連続して宿泊サービスを提供する日数の上限は、原則30日とすること」と独自の基準が定められています。
お泊まりデイサービスは長期間の利用を前提としたサービスではないため、長期滞在や連泊を希望される方が一定数を超える場合、ショートステイをはじめとした別の介護保険サービスを検討しなければならないケースは十分に考えられます。
参照:指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について 平成27年4月厚生労働省
参照:大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営について
お泊りデイサービスを利用する場合、介護保険外サービスのため全額自費負担になります。利用料金の相場は、おおよそ1泊3,000円〜5,000円です。
利用料金は、介護保険サービスのように基準がありません。要介護度や部屋のタイプによっても料金は変動し、事業所によっては1泊食事込みで1000円前後の宿泊料金を設定している場合もあります。
ただし、低額に抑えられているお泊まりデイサービスにおいて、問題が生じるケースは少なくありません。介護・保育ユニオンという労働組合では以下のように問題点を指摘しています。
お泊りデイは、利用料が低額に抑えられているため、採算をとるためにはケアワーカーに無理をさせる運営を行い、労働条件に矛盾がしわ寄せされてしまっている事例が数多くあります。
参照:介護・保育ユニオン
しかし、問題のあるサービス提供をする事業所だけが存在している訳ではありません。利用時間や基本サービスに至るまで、細かくサービス内容を公表している事業所もあります。
利用者とその家族のニーズが高いお泊まりデイサービスは介護保険外サービスであり、全額自費負担で利用できます。ただし、利用料金を含め、サービス内容の自由度も高い点に注意する必要があるでしょう。
厚生労働省よりガイドラインが発出されたことにより、以前よりも安全性や品質の確保、利用者の権利保護を重視した宿泊サービスの運営が促進されています。
しかし、保険外サービスであることから、いくつかの課題を抱えているのも事実です。
具体的には、以下のような課題が存在します。
上記のような課題は残っていますが、厚生労働省からガイドラインによる規制が敷かれる以前はルールが存在しておらず、より多くの問題を抱えていました。ガイドライン以前に比べると、少しずつ問題は解消されつつあるといってよいでしょう。
お泊まりデイサービスは介護保険外のサービスであるからこそ、ガイドラインを遵守し、より一層利用者や家族が安心して利用できる運営が求められます。
お泊まりデイサービスを利用する際は、本記事で紹介している情報をもとに各施設のサービス内容をチェックすると良いでしょう。
参照:通所介護事業所の設備を利用した介護保険制度外の宿泊サービスの提供実態等に関する調査研究事業報告書 平成28年3月三菱UFJリサーチ&コンサルティング
お泊まりデイサービスの運営について、東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課のQ&Aを一部抜粋してご紹介します。
届出について
Q|基準を満たさないと届け出られないのか。
A|この届出が行われないと、指定通所介護事業所としての基準違反になります。必ず届け出てください。基準を満たさないことにより届け出られないことはありませんが、当該基準は宿泊サービスを提供する場合における遵守すべき事項を定めたものです。事業所には適合するよう改善することが求められます。(基準 第1の1)
Q|宿泊サービス事業の届出に当たり、建築基準法、消防法、労働基準法など他法令に適合している必要があるのか?
A|宿泊サービスを提供するに当たっては、指定通所介護サービス事業等だけでなく、夜間に利用者を宿泊させる事業を行うことを含めた法令の遵守が求められます。詳しくは、それぞれの法令所管部署にご相談ください。(基準 第1の4(4))引用:東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課(平成27年6月)「東京都における指定通所介護事業所等における宿泊サービスの基準及び届出・公表制度」について【Q&A】
公表について
Q|宿泊サービス事業者の情報はどのように公表されるのか
A| 介護サービス情報の公表制度(https://www.kaigokensaku.jp/)において、通所介護の「基本情報」の中に宿泊サービスに関する項目が追加されます。また、当面の間、都のホームページ「東京都介護サービス情報」において公表します。(基準第4の20(1)、同(5))引用:東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課(平成27年6月)「東京都における指定通所介護事業所等における宿泊サービスの基準及び届出・公表制度」について【Q&A】
総則について
Q|日中、他の事業所や自宅等を利用する者が宿泊サービスを利用することは可能か?
A|宿泊サービスは通所介護事業者の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所の利用者に対しサービスを提供するものです。日中に当該通所介護事業所を利用者しない者が利用することは想定されていません。(基準 第1の2(1)・(4))
Q|長期間連泊を希望する利用者に対しては、どうしたらよいか?長期に宿泊し、(居宅がないなど)帰宅できない状況の利用者への対応はどうしたらよいか?
A|在宅サービスである指定通所介護事業所等の設備を利用して提供する宿泊サービスについては、緊急かつ短期的な利用に限定されるべきであり、宿泊サービス利用を長期化させるべきではありません。宿泊サービス事業者は、基準に沿ったサービス利用となるよう、利用者の担当の介護支援専門員と十分に連携する必要があります。なお、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情により連続した利用が予定される場合においては、指定居宅介護支援事業者や区市町村と密接に連携を図った上で、他の介護保険サービスへの変更を含め、利用者の心身の状況や利用者の家族の事情等に応じたサービス提供を検討してください。(基準 第1の3(2)・第1の4(3))引用:東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課(平成27年6月)「東京都における指定通所介護事業所等における宿泊サービスの基準及び届出・公表制度」について【Q&A】
人員に関する基準について
Q|宿泊サービスの内容に応じ必要数を配置するとあるが、従業員の配置はどうしたらよいか?
A|本基準においては、宿泊サービス提供時間帯を通じて1人以上と定めていますが、介護・宿泊等の適正なサービス提供はもとより、緊急時にも適切に対応し、安全な運営が必要です。特に、朝食及び夕食の時間や就寝・起床準備の時間帯等の繁忙時間帯においては、事業所ごとの実状に応じて必要人数を配置してください。(基準 第2の1)
Q|夜間、利用者の就寝時間帯における配置人員について、宿直勤務者を従業者として配置することは可能か?
A|宿泊サービス事業所の従業者は、利用者の就寝時間中においても、排せつ介助や安全確保のための見守り等の介護に係るサービスを、適切に提供しなければなりません。また、労働基準法では「宿直」とは、所定労働時間外における勤務の一態様であって、本来の業務は処理せず、緊急の電話の収受や非常事態に備えて待機するもので、常態としてほとんど労働する必要のない勤務態様と解されています。したがって、宿泊サービス事業所において行うべきサービス提供は事業本来の業務であり、労働基準法上の「宿直」にはあたらないため、宿直勤務者は、従業者の員数に含まれません。
Q|「資格を有する者」とは、どのような資格か?「介護に関し知識及び経験を有する者」とは、どのような意味か?
A| 宿泊サービス提供においては、夜間、複数の利用者に対し、原則1人の従業者が介護等のサービスを提供するものであることから、介護福祉士、介護職員実務者研修、介護職員初任者研修課程を修了した者等の利用者への直接処遇に関する専門的知識や、介護の提供に係る経験を有する者が望ましいと考えています。
Q|緊急時の対応について、具体的にどのような体制が必要か?
A|宿泊サービス提供時間帯を通じて夜勤の従業者以外に、利用者の容態急変や災害発生の緊急事態に対応できる支援要員を確保する体制です。具体的には、宿直勤務者やオンコール体制(夜間に自宅などで待機して、緊急の呼び出しに応じて事業所へ出向き応援できる体制)などです。(基準 第2の1の(4))引用:東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課(平成27年6月)「東京都における指定通所介護事業所等における宿泊サービスの基準及び届出・公表制度」について【Q&A】
責任者について
Q|指定通所介護事業所等の管理者は、宿泊サービスの責任者になれるか?
A|指定通所介護事業所等の従業者が、宿泊サービス従業者として勤務する場合は、指定通所介護事業所等の人員基準及び労働基準法に違反しない範囲において、当該従事者を責任者とすることは可能です。引用:東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課(平成27年6月)「東京都における指定通所介護事業所等における宿泊サービスの基準及び届出・公表制度」について【Q&A】
必要な設備及び備品等について
Q|必要な消防設備とは何か?
A|1ヶ月に5日以上宿泊サービスを提供する事業所は、「消防法施行令別表第1(6)項ロ」が適用されるため、防炎クロス・カーテン、誘導灯、消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備が必要です。消防用設備の詳細については、最寄りの消防署にご確認ください。
Q|「宿泊サービスを提供するにあたり適切な寝具等の必要な備品」とは何か?
A|各事業所における宿泊サービスの提供を行うにあたり、必要となる設備を指します。指定通所介護事業所等の設備・備品については、その運営に支障のない範囲であれば、使用しても差し支えありません。なお、例えば宿泊サービス提供用の折りたたみベッドを事業所内に保管する場合などに、指定通所介護事業所のサービス提供時間帯において食堂兼機能訓練室等基準に定める設備に影響しないよう、注意してください。引用:東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課(平成27年6月)「東京都における指定通所介護事業所等における宿泊サービスの基準及び届出・公表制度」について【Q&A】
宿泊室について
Q|指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供することは可能か?
A|「指定通所介護事業所の設備を利用しないもの」、または「食堂などの一部設備を共用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施するもの」は宿泊サービスには該当しません。ただし、これらの形態は有料老人ホームとして老人福祉法上の届出が必要になる場合があるので注意してください。
Q|宿泊室における一人当たりの床面積7.43㎡について、広すぎる(狭すぎる)のではないか?
A|利用面積の基準については国指針に準拠して定めています。従来の都の独自基準においても、小規模多機能型居宅介護の宿泊室の1室あたりの床面積7.43㎡以上の基準をもとに、指定通所介護事業所等の利用定員及び1人当たりの面積等を勘案して同様の基準を定めていました。利用者の尊厳保持及び安全確保を図るために、必要な面積であると考えています。
Q|個室以外の宿泊室の面積や利用者ごとのスペースの確保の考え方は?
A|個室以外の宿泊室は、当該事業所内に個室がない場合においても、宿泊室としてプライバシーが確保されたしつらえで必要面積が確保されていれば差し支えないとしています。台所、廊下、玄関ホール、脱衣所等の居室以外の面積は含まれないこと、また、本基準の「個室以外の宿泊室」の面積と指定通所介護事業所等の「食堂兼機能訓練室」の届出面積とは直接関係ないものであることにご注意ください。なお、個室以外の宿泊室の面積においては、宿泊室に隣接する他の利用者等が通らない縁側等のスペースがある場合には、利用者の占有スペースに含めることができます。
Q|個室以外の宿泊室において、利用者のプライバシーが確保された構造が必要とされているが、具体的にはどのようなものか。
A|個室以外の宿泊室については、プライバシーの確保された構造とは、パーティションや家具などにより、利用者同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要があります。アコーディオンカーテンにより仕切られている宿泊室については、パーティションや家具などと同様にプライバシーが確保されたものである場合は、宿泊室として取り扱って差し支えないと考えます。ただし、カーテンについてはプライバシーが確保されたものとは考えにくいことから認められません。
Q|宿泊室は2つのフロア(1階と2階など)にそれぞれ設けてもよいか?
A|適切かつ安全なサービス提供を行う必要があるため、異なるフロアに宿泊室を設けた場合、サービス提供時間帯を通じて複数の従業者を配置すること等の配慮が必要です。引用:東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課(平成27年6月)「東京都における指定通所介護事業所等における宿泊サービスの基準及び届出・公表制度」について【Q&A】
運営について
Q|宿泊サービス計画作成について、注意すべきことはどのようなことか?
A|特に以下の点についてご注意ください。
●4日未満の利用であっても反復的、継続的に利用することが予定されている利用者については、宿泊サービス計画を作成してください。
●居宅サービス計画に沿って作成し、宿泊サービスの利用が長期間とならないよう、居宅介護支援事業等と密接な連携を図ってください。
●計画の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画を利用者に交付してください。
Q|【主治医等との連携、緊急時等の対応、非常災害時の対応、事故発生時の対応について】
これらについては、すべて個別にマニュアル等を作成する必要があるのか?
A|本基準においては、それぞれの事態に対応した連絡・連携について求めています。有事に円滑に対応する備えを行うためには、これらについてマニュアルや手順書等の整備が望まれます。マニュアルや手順書等の体裁については、事業所ごとの実態に即して作成してください。なお、「主治医等との連携」とは宿泊サービス計画策定時や必要な場合に利用者の心身の状況について情報連携を行うこと、「緊急時等の対応」とは宿泊サービス提供時に利用者の病状の急変等のあった場合の対応、「非常災害対策」は地震や火災等の非常災害発生時の対応、「事故発生時の対応」とは宿泊サービスの提供により事故が発生した場合の対応をいいます。
Q|【事故発生時の対応】介護保険外の宿泊サービス利用中の事故においても、市町村や居宅介護支援事業所へ連絡する必要があるのか?
A|宿泊サービスは、居宅介護支援事業者との連携により提供されるべきものです。また、宿泊サービス事業者は区市町村の調査等に協力することが求められています。事故発生時には速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者に連絡し、必要な措置を講じて下さい。なお、宿泊サービスにおける事故発生時の対応については、指定通所介護の基準にも定められており、適切な対応がない場合は指定通所介護事業所としての基準違反にもなります。
その他、以下の点にも留意して下さい。
●事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は2年間保存すること。
●宿泊サービスの提供により事故が発生した場合の対応方法についてあらかじめ事業者が定めておくことが望ましい。
●速やかな賠償のために損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましい。
●事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。引用:東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課(平成27年6月)「東京都における指定通所介護事業所等における宿泊サービスの基準及び届出・公表制度」について【Q&A】
お泊まりデイサービスは、介護が必要な方にとって、新たな宿泊サービスの選択肢となっています。利用者の心身の状況や利用者の家族の負担軽減などに対応し、介護保険外のサービスとして提供されているサービスです。
ショートステイなどの介護保険を利用した宿泊サービスの空きが少ない場合には、お泊まりデイサービスが一つの選択肢となるでしょう。
課題もありますが、厚生労働省の指針に基づき、品質向上が進められています。高齢者や介護が必要な方にとって、昼夜ともに安心して生活を送るための選択肢として検討してみると良いでしょう。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

コラム
2024/04/19

コラム
2024/04/18

コラム
2024/04/18

コラム
2024/04/18

コラム
2024/04/18
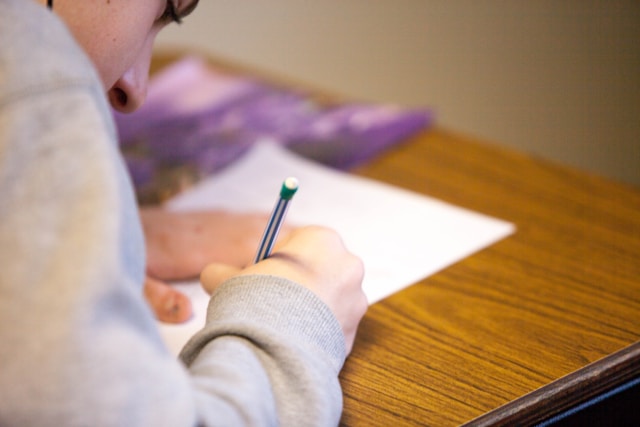
コラム
2024/04/17