「介護×ICT」で現場はどう変わる?メリットと導入事例・今後の展望
運営ノウハウ
2024/04/18
運営ノウハウ
人材
更新日:2023/06/15
デイサービスでは人員配置で生活相談員や介護職員、看護職員の配置が必要になっていますが、急な欠勤で休みになってしまい、不在になる可能性もあります。人員配置が必須の職種が急な欠勤で休みになってしまった場合、どのように対応したら良いかをご紹介します。
→科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
→無料研修会「リハビリ支援ソフト「Rehab Cloud リハプラン」デモンストレーション会」
この記事の目次
デイサービスでは、利用者の安全と適切なケアを確保するために、人員配置の基準が存在します。しかし、病欠や忌引きなどの理由で人員配置が基準を満たせなくなるケースは決して少なくありません。
病欠や忌引きで人員配置基準を満たせない場合であっても、基準を守らなければ人員配置基準違反となってしまいます。
このような人員不足の状況に直面した場合、施設は迅速かつ適切な対処策を講じなければなりません。たとえば、スタッフのシフト変更や兼務などの対策が考えられます。
ただし、欠勤や欠員の発生に対しては柔軟かつ迅速な対応が求められるため、計画的な人員管理と予備の配置を行うことが重要になります。
人員基準欠如減算はデイサービスの運営において重要な要素であり、理解しなければ大きな損害を被りかねません。
ここでは、職員が欠勤した場合や、欠員になった場合の対処について解説します。
「稼働率を向上させる「働きやすい職場づくり」のコツ 」がわかる資料(PDF)を無料プレゼント中!
「デイサービスの業務効率化の手引き」がわかる資料(PDF)を無料プレゼント中!
適切にデイサービスに人員配置するためには、欠勤と欠員の考え方を理解する必要があります。
欠員とは、そもそも勤務する人がいない状態を指します。つまり、必要な人員が配置されておらず、業務が遂行できない状態です。たとえば、必要なスタッフの採用がまだ行われていない場合や、退職や移動などによる人員基準欠如のある場合が該当します。
一方、欠勤は勤務している従業員が病気や忌引きなどの理由で不在になる状態を指します。欠勤は予測できない事態ではありますが、容認されるものではありません。人員基準欠如とみなされ、減算に該当する場合があるため、注意が必要です。
デイサービスにおいて、必要な人員配置が欠如した場合、人員基準欠如減算の対象になります。欠如があった月の翌月、利用者全員に請求する単位の30%が減算されます。
欠勤・欠員は算定の問題のみではありません。欠勤が続くと、人員配置の問題がさらに深刻化し、サービス提供に影響を及ぼす可能性が出てくるでしょう。
人員配置の管理には十分な注意が必要です。適切な人員配置を確保するためには、スタッフの採用や教育体制の整備、予備のスタッフの確保など、積極的かつ計画的な取り組みが求められます。
欠勤と欠員に関する考え方を理解し、適切な人員配置を確保することは、品質を保ったサービス提供を実現するために欠かせません。人員配置の管理は、サービスの安定性や利用者の満足度に直結します。
通所介護サービスを提供するために必要な人員基準について、職種ごとに紹介します。以下の内容が厚生労働省介護給付費分科会より発表されている人員基準です。
| 人員基準 | ||
|---|---|---|
| 生活相談員 |
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上(常勤換算方式)(生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能) |
|
| 看護職員(※) |
単位ごとに専従で1以上(通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能。) |
|
| 介護職員(※) |
① 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上(常勤換算方式) |
|
| 機能訓練指導員 |
1以上 |
|
|
生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤 |
||
※定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可(常勤換算方式)
参考:通所介護・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護(社保審-介護給付費分科会)
以下にさらに細かく解説します。
人員基準欠如減算の減算割合は30%であり、非常に大きいです。また、同様の減算割合である定員超過利用減算というものもあります。通所介護を運営する上で抑えておくべき事柄をここで詳しく解説しますのでご参考ください。
人員基準欠如減算とは、その介護施設や介護サービスに必要な人員配置が行われていない場合に適用される減算措置のことを指します。
通所介護において、必要な人員配置が欠如した場合、人員基準欠如減算の対象になります。人員が欠如した月の翌月、利用者全員に請求する単位の30%が減算されます。
人員基準欠如に該当する場合などの所定単位数の算定については「職員配置等基準において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、適正なサービス提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。」という前提があり、人員基準を満たさない状態で運営を続けることは許容されません。
人員基準欠如が続いた場合は、指定取り消しなどの処分を受ける可能性があるので注意しましょう。
看護職員の人員基準欠如に該当する状態は、通所介護サービスを提供するために必要な看護職員の人員基準を満たさない状態を指します。
よって、まずは通所介護における看護職員の人員基準を理解する必要があるでしょう。
通所介護における看護職員の人員基準は「単位ごとに専従で1以上」とされています。ただし、注釈として「通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能」とされています。
つまり、通所介護を運営している時間帯の全てにおいて看護職員が専従で必要と言う基準ではありません。
病院や訪問看護ステーションと密接に連携して通所介護の営業日に利用者の健康状態を確認できるサービス提供体制であれば人員基準を満たしたことになります。
また、定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は「看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可(常勤換算方式)」とされています。よって、その場合は介護職員が常勤換算で1以上配置されていれば看護職員を配置しないことも可能と判断できるでしょう。
看護職員の人員基準欠如に該当する状態は上記の基準を満たさないケースと理解できます。
たとえば
などが挙げられるでしょう。
看護師の配置基準については、以下の式で表すことができます。
「サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日」
1.計算式の値が1より少なく0.9以上の場合
その翌々月から人員欠如が解消される月まで減算
(翌月末に人員欠如が解消した場合は減算とはならない)
2.計算式の値が0.9より少なくなる場合
その翌月から人員欠如が解消される月まで減算
上記の式を満たす配置ができるように注意しましょう。
介護職員の人員基準欠如に該当する状態は、通所介護サービスを提供するために必要な介護職員の人員基準を満たさない状態を指します。まずは通所介護における看護職員の人員基準を理解するようにしましょう。
通所介護の介護職員の人員基準は以下のように決められています。
上記の基準を満たさない場合に人員基準欠如に該当しますが、介護職員は常勤換算方式で計算する必要があります。計算式などを理解する必要があるため、以下に詳しく解説します。
常勤換算方式は、1ヵ月の介護職員の勤務形態や時間を換算し「常勤職員が何人働いたことになるか」という考え方で計算する方法です。
常勤換算を計算する式は以下のようになります。
1ヵ月間の稼働時間数÷常勤の1ヵ月間の勤務時間数=常勤換算人数
具体例を挙げて考えていきましょう。
たとえば、常勤職員の勤務体制が一般的な「1日8時間、週5日」だったとしましょう。
その場合、常勤職員は1ヵ月(4週間)で160時間働く計算になり、この時間数が常勤換算で1名ということになります。
ある介護施設に「1日8時間、週5日」働く常勤介護職員3人と、「1日4時間、週5日」パートタイムで働く介護職員2人がいる場合、常勤換算方式を用いて計算すると合計4人分の常勤換算数になります。
合計4人分になる計算を式で表すと以下のとおりです。
といった計算になります。常勤換算を計算する式に合わせると以下のようになります。
1ヵ月間の稼働時間数(540時間)÷常勤の1ヵ月間の勤務時間数(160時間)=常勤換算人数(4人)
上記が常勤換算の考え方になります。これらの考え方を踏まえた上で「サービス提供時間に応じた人数」を考慮して計算する必要があります。
ここで、人員基準欠如減算になるケースを例に挙げてみましょう。
利用者人数が30人、サービス提供時間が7時間の場合は以下の計算が必要になります。
(0.2✖️15)人+1人✖️8時間≦介護職員の勤務時間数
計算すると、介護職員の勤務時間数は32時間以上必要です。よって最低でも8時間働く常勤職員3名と、4時間働くパート職員2名ほどの人材が必要になるでしょう。
生活相談員の人員基準を満たせていない場合は、人員基準欠如減算の対象にはなりませんが、人員基準違反で指導・処分される可能性があります。
生活相談員は介護サービスの計画や相談支援など重要な役割を担っており、その人員基準を満たせていない場合は、介護保険サービスの提供要件を満たせていない状態となります。
また、生活相談員以外の職種においても人員基準を満たさずに営業することは適切ではありません。
人員基準を満たさない場合には、介護保険課から営業制限や介護報酬の減額などの措置が取られる可能性があります。通所介護における生活相談員の人員配置は、サービス提供時間に応じて専従で1以上となっており、資格要件もあるため、注意しましょう。
欠員が予め分かっている場合は、他の職員が兼務することで一時的に人員不足を補うことができます。
たとえば、管理者などが一時的に機能訓練業務を兼務することで、人員の配置を調整することができます。
どうしても人員不足が解消できない場合は、介護保険課に相談して指導を仰ぐほうが良いでしょう。介護保険課は適切な介護サービスの提供を支援するための機関であり、人員不足に関する問題に対して適切な指導やアドバイスを提供してくれるはずです。
基本的に人員基準を満たさずに不適切な状態で営業を続けることは許容されません。介護保険課の指導のもと、適切なサービス提供を心がける必要があります。
営業を続けることが困難な場合は、介護保険課に人員不足の状況を正確に伝え、判断を仰ぐことが重要です。
介護保険課は現場の状況を考慮し、例外的な営業を許可する場合や営業を中止する判断を下すことがあります。適切な判断をもらうことで、利用者に対する適切なサービス提供や職員の負担を考慮した営業管理が行われます。
人員を調整できない場合は「例外的に営業する」もしくは「営業を中止する」かの判断を介護保険課にしてもらうのが健全です。
人員基準欠如が認められた場合、加算が取れなくなったり減算されたりする可能性があるので注意が必要です。
人員基準欠如が長期化したり、継続的な問題となったりする場合は、経営や運営の面からも対策を検討する必要があるでしょう。
介護現場では、急な病欠や忌引きなどの理由により、人員が足りなくなることがよくあります。これは一般的であり、どの施設でも起こり得ることです。
人員不足の対策として、介護職員や管理者が兼務する形で生活相談員の業務を担当することは良くあります。兼務をすることで一時的な人員不足に対応でき、サービスの継続性を確保することができます。ただし、兼務の場合でも介護サービスの質の確保には注意しましょう。
人員不足に対して適切な代替手段が取られていない場合、介護保険課から厳しい指導を受ける可能性があるでしょう。
介護施設や事業所は、常に人員不足への備えや代替策を検討し、適切な人員配置を確保する責任があります。場合によっては指定の取り消し処分を受けることもあり得ます。
そのため、生活相談員の人員基準を満たす資格を持つ人員を採用するなどの対策を講じる必要があります。
緊急の場合や一時的な人員不足に対しては、兼務や代替手段など臨機応変な対応が求められますが、長期的な安定した人員配置を確保することが重要です。
人員不足に対するリスク管理や計画的な採用活動、スタッフの教育・研修などを通じて、人員基準欠如減算のリスクを軽減し、適切な介護サービスの提供を継続することが求められます。
人員基準欠如が調整できない場合、運営する事業所は運営(実地)指導をする行政に相談することが重要です。運営指導によって人員不足が指摘されると、それは「人員配置違反」となり、指導・処分される可能性があります。
人員配置基準を満たさないまま運営すると、事業所の管理者が責任を負うことになります。事業所の存続と適切な介護サービス提供のためには、行政の指導を仰ぎ、正しい見解を得て対策を練ることが重要です。
適切な介護サービスの提供を継続するため、人員不足には早急に対処し、法令遵守と安定的な人員配置に努めることが求められます。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

運営ノウハウ
2024/04/18
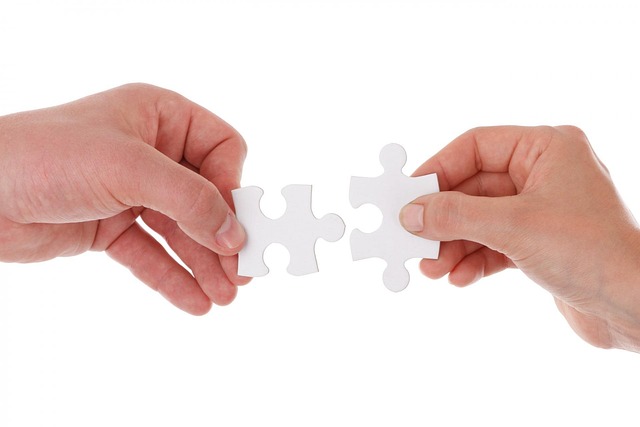
運営ノウハウ
2024/04/18

運営ノウハウ
2024/04/18

運営ノウハウ
2024/04/17

運営ノウハウ
2024/04/17

運営ノウハウ
2024/04/17