BMIの計算方法と標準値|高齢者の平均体重から分かる肥満や低体重
現場ノウハウ
2024/04/23
現場ノウハウ
資格・職種
更新日:2024/04/15
特別養護老人ホーム(以下、特養)で働く機能訓練指導員は、どのような仕事をするのか、どのような特徴があるか知っていますか?特養の機能訓練指導員の主な仕事は、生活リハビリです。今回は、そんな特養の機能訓練指導員について、その特徴や仕事内容、個別機能訓練加算の算定要件や算定率についてまとめてご紹介します。
この記事の目次

特養における機能訓練指導員とは、ご高齢者が住み慣れた環境で生活するために必要な身体機能や食事やトイレなどの日常生活動作(ADL)、料理や洗濯などの家事動作(IADL)、趣味、社会参加を獲得するために必要な個別の機能訓練(リハビリ)を提供する職種のことを指します。
ちなみに、平成29年の特養の人員基準では、入居者100人につき機能訓練指導員が「1人以上」配置をすることが定められています。
そもそも機能訓練指導員という資格はなく、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、6ヵ月以上の実務経験を持つ鍼灸師(はり師・きゅう師)の8つのいずれかの資格を有する職種を機能訓練指導員と呼びます。
| 【平成30年度改訂】平成30年度介護報酬改定において、はり師・きゅう師が機能訓練指導員として追加されました。 |
▼機能訓練指導員のそれぞれの職種の特徴については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
| 【関連記事】 機能訓練指導員とは|資格要件や仕事内容をご紹介【平成30年度改訂版】 平成30年度の機能訓練指導員の資格要件の緩和も含めて、職種ごとの仕事内容の違いや魅力、給料を詳しくまとめてご紹介します。 |

特養(介護老人福祉施設)では、主に在宅での生活が難しく、長期に施設入所が必要な介護度の高い(要介護3~5)入居者様が多くを占めています。そのため、特養の機能訓練指導員は、積極的な運動を行うというよりも、着替えやトイレ、お風呂など生活に即した訓練(通称:生活リハビリ)を行っていることが特徴です。
▼特養の機能訓練指導員が行う「生活リハビリ」について知りたい方は以下の記事で詳しくご紹介しています。生活リハビリについて知りたい方はこちらをご覧ください。
| 【関連記事】 生活リハビリとは 生活リハビリの考え方やその種類、生活リハビリをする上でのポイントについて解説します。 |

特養の機能訓練指導員の主な仕事内容には、「生活リハビリ」があります。
例えば、特養に入居するご利用者様が「トイレ」を行う場合には、機能訓練指導員は以下のような手順で「生活リハビリ」に取り組みます。
▼特養の機能訓練指導員が作成する計画書については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。興味がある方はこちらをご覧ください。
| 【関連記事】 個別機能訓練計画書の書き方について|初めて計画書を作成するあなたへ 個別機能訓練加算Ⅰまたは個別機能訓練加算Ⅱを算定するために必要な個別機能訓練計画書の書き方についてまとめてご紹介します。 個別機能訓練計画書で悩む!目標設定の仕方から書き方を徹底解説します 個別機能訓練計画書の中でも「目標設定」に着目して、情報収集の仕方から目標設置の仕方・書き方までを徹底解説します。 個別機能訓練計画書の基本情報の書き方 個別機能訓練計画書の中でも「基本情報」に着目して作成方法をご紹介います。 |

特養で機能訓練指導員を配置、かつ機能訓練指導員が中心となって生活リハビリなどの機能訓練を計画的に提供することでどのような加算を算定できるのでしょうか?
| 【特養の個別機能訓練加算の単位】単位数 12単位/日 |
特別養護老人ホームで算定できる「個別機能訓練加算」については「特別養護老人ホーム(特養)の個別機能訓練加算の算定要件・計画書」で紹介しています。
ちなみに、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)および地域密着型介護老人福祉施設における個別機能訓練加算の算定率(推計)は「49.38%」です。
意外にも、約半数の施設で算定しています。
| 【関連記事】 特養における個別機能訓練加算とは|算定要件から計画書作成まで解説 約半数の福祉施設で算定されている個別機能訓練加算について算定要件から計画書作成まで解説していきます。 |

では実際に、特養で個別機能訓練加算を算定する場合は、どのような算定要件が必要となるのでしょうか?
【特養の個別機能訓練加算の算定要件】
次の基準にすべてに適合することが条件です。

平成30年度介護報酬改定では、ご高齢者がその人らしく暮らせる「自立支援」へと大きく舵を切ろうとしています。そのため、特養においても機能訓練指導員の役割が重要視されていきます。
実際に特養だけではなく、デイサービスや介護老人福祉施設なども機能訓練指導員が1名以上配置することが義務付けられています。
機能訓練指導員は、ご利用者様が住み慣れた環境で、その人らしく生活を送り続けられるように機能訓練を提供するお仕事です。
皆さんも特養の機能訓練指導員として、いつまでも元気なご高齢者の支援をしていきませんか。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。
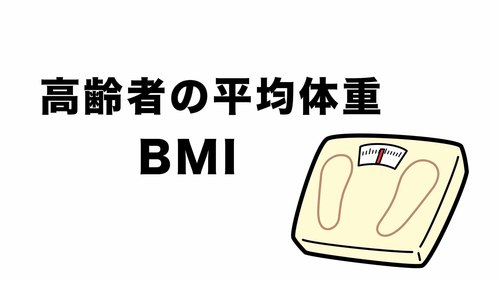
現場ノウハウ
2024/04/23

現場ノウハウ
2024/04/23

現場ノウハウ
2024/04/23

現場ノウハウ
2024/04/23
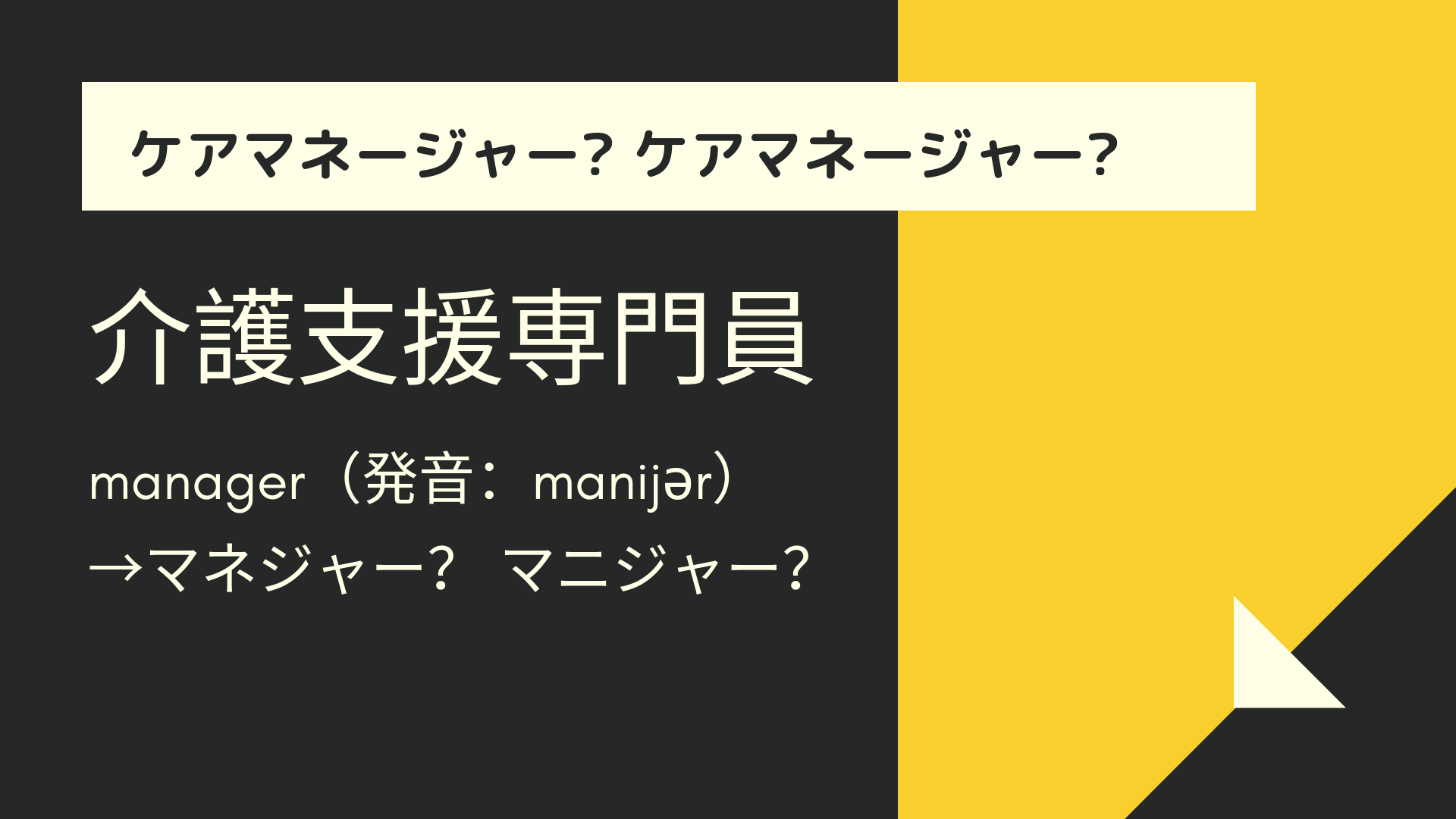
現場ノウハウ
2024/04/23

現場ノウハウ
2024/04/23