BMIの計算方法と標準値|高齢者の平均体重から分かる肥満や低体重
現場ノウハウ
2024/04/23
現場ノウハウ
評価
更新日:2024/04/15
FIMの認知項目の中でもコミュニケーションである「理解」「表出」が難しいと悩んでいる方はいませんか?FIMのコミュニケーション項目は、音声(非音声)、聴覚、視覚(ジェスチャーなど)により意思疎通を図る際の理解状況または、言語表出を評価します。今回はこの「理解」「表出」の2項目の採点方法について解説します。
→科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
→無料研修会「リハビリ支援ソフト「Rehab Cloud リハプラン」デモンストレーション会」
この記事の目次

FIMの認知項目であるコミュニケーションには「理解」と「表出」の2種類があります。
こちらの評価・採点方法をご紹介する前に、認知項目であるコミュニケーション(理解・表出)の基本的な採点基準を解説します。
【FIMの認知項目の採点基準】
◎7点(完全自立)
◎6点(修正自立)
◎5点(監視・補助・最小介助)
◎4点(最小介助)
◎3点(中等度介助)
◎2点(最大介助)
◎1点(全介助)
FIMの運動項目と大きく異なるポイントは、5点の採点基準が監視・補助だけでなく「介助が10%未満」も含まれることです。
▶︎FIMを初めて評価する方はこちらの記事がオススメです。
| 【関連記事】 FIMとは|FIMの評価方法と点数付けで知っておきたい基礎知識【総論】) FIMの特徴や評価項目などの基礎知識から採点方法までかんたんに解説します♬ |

それでは、具体的にFIMのコミュニケーション項目である「理解」の採点を行う場合のポイントをご紹介します。

では、実際の現場で採点することが難しいと感じることの多い、難聴の場合のFIMのコミュニケーションである「理解」の採点事例をご紹介します。
▶︎事例1
耳が遠いため補聴器などの使用していれば、複雑な内容が理解できる
▶︎事例2
耳が多いため日常生活で少し大きな声で話しかければ、複雑な内容が理解できる
▶︎事例3
難聴もあり、意識状態もムラがあるため声かけをしても反応に乏しく理解できない

次に、悩むことが多いのが失語症の場合です。失語症の場合は、言葉が分かっているのか判断がつかない場合があるのではないでしょうか?そこで、失語症の場合のFIMの理解の採点事例をご紹介します。
▶︎事例1
テレビ番組や新聞記事の内容など複雑な内容を理解できるがわかりやすく話す必要がある
▶︎事例2
金銭、社会問題などに関する会話を繰り返し行うと理解できる
▶︎事例3
日常会話の内容を普通に説明するとだいたい(75%以上)の内容を理解できる
▶︎事例4
日常会話の内容を短い語句で説明すれば理解できる
※基本的に失語症で、言葉が理解できているか判断できない場合は、理解できている割合より、話をする側の配慮がどれくらい必要かの割合を考えて採点する方が実用的とされています。

では、続いてFIMのコミュニケーション項目の中でも「表出」の採点を行う場合のポイントをご紹介します。

FIMの「表出」の項目の中でも失語症の場合の採点事例をご紹介します。
▶︎事例1
日常生活についてははっきりと伝えることができるが、失語症のため金銭的なことや退院後のことについては議論することができなかった。
▶︎事例2
物を指差して「私に下さい」と言えるが、失語症のため服が欲しくても「帽子をください」と間違えることが1/3回はある。
▶︎事例3
失語症がありジェスチャーで日常の用を伝えている。

FIMの評価の中でも認知項目であるコミュニケーション・社会的認知項目の採点が難しいと思われる方も多いのではないでしょうか。座学で正しいFIMの採点方法を学んだ後は、実際の症例に点数をつけていき、他のスタッフの点数との違いを話し合うことで採点の精度を高めていきましょう!
デイサービス運営において必要な「評価・測定」について、一挙にまとめていますので、必要に応じて活用していただければと思います。
→→ 【完全保存版】デイサービスで活用できる評価・測定に関する記事まとめ|随時更新
▼コミュニケーション(理解・表出)を学んだ後は、合わせて社会的認知(社会的交流・問題解決・記憶)の採点方法も学んでみませんか?FIMの社会的認知の採点方法については下記の記事をご覧ください。
【終わりに筆者より】
リハプラン では、FIMの採点方法以外にも介護現場で活用できる評価方法についてご紹介しています。「この評価はどう採点したらいいの?」などお悩みがありましたら専門家に直接相談することもできます。ぜひ一度ご相談ください♬
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。
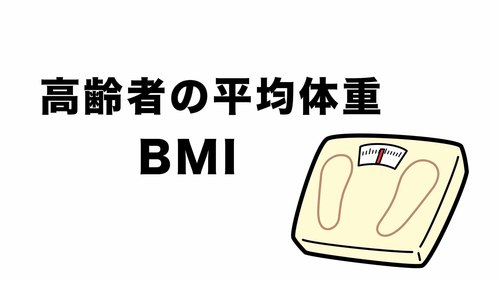
現場ノウハウ
2024/04/23

現場ノウハウ
2024/04/23

現場ノウハウ
2024/04/23

現場ノウハウ
2024/04/23
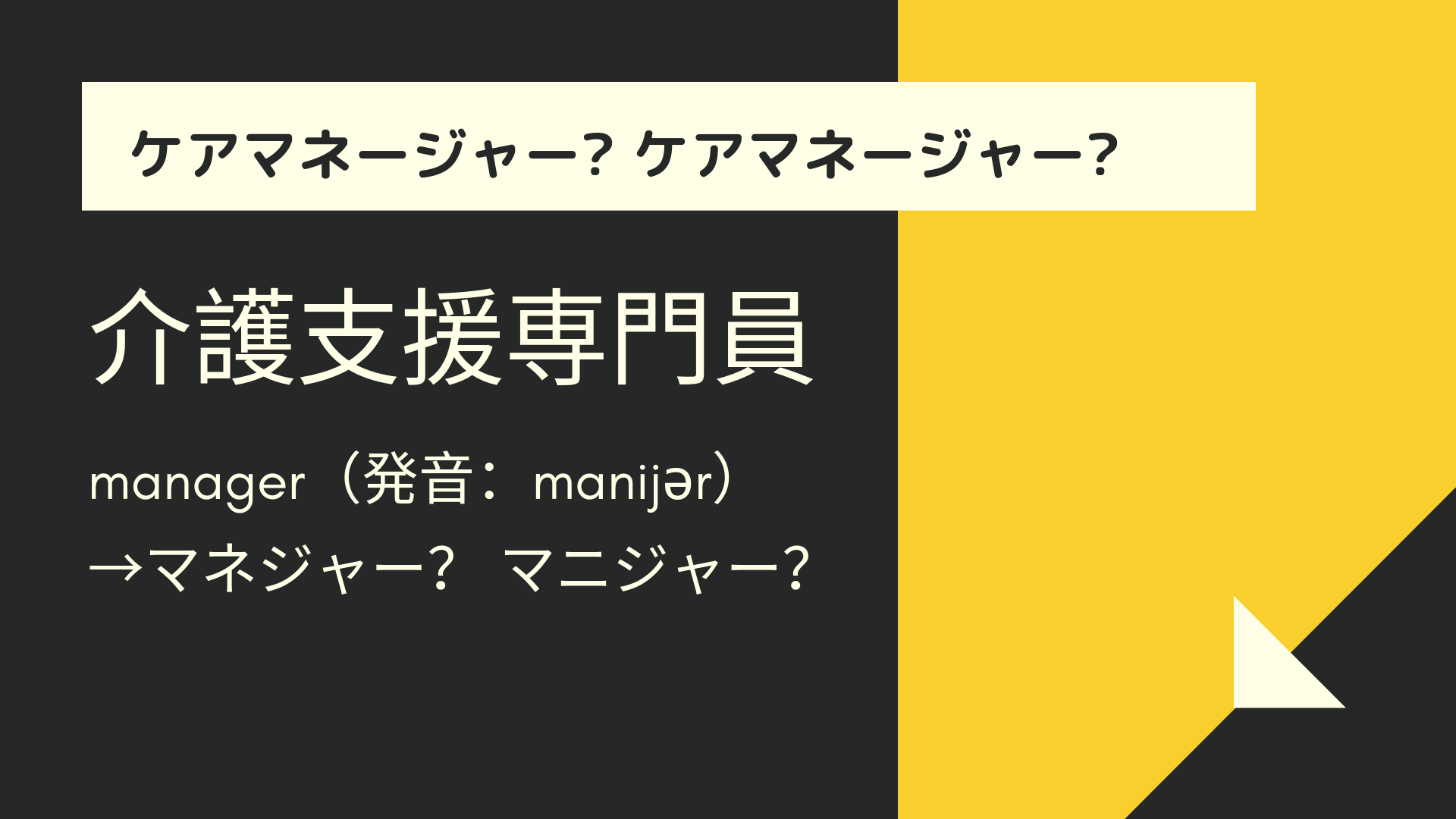
現場ノウハウ
2024/04/23

現場ノウハウ
2024/04/23