【実践】嚥下体操で口腔ケア!毎日の健康維持に役立つ方法
機能訓練
コラム
2024/04/11
機能訓練
下肢
更新日:2024/04/09
片脚立位の評価方法やカットオフ値を知っていますか?今回は、バランス評価の中でも簡便に検査できる片脚立位について測定方法から評価の指標となるカットオフ値まで紹介します。身体機能評価の1つとして参考にしてみましょう。
この記事の目次
▶科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!

片脚立位の評価とは、片脚立ちで姿勢を保っている時間を測定する簡易なバランス検査です。片脚立位の評価方法には、目を閉じて測定する「閉眼片脚立位」と目を開けて測定する「開眼片脚立位」の2種類があります。特に、ご高齢者に測定する場合は、「開眼片脚立位」で測定するのが一般的です。
片脚立位の評価は、日本整形外科学会でもTUGの評価と共に「運動器不安定症状」を診断する機能評価基準の1つとして指定しています。
–機能評価基準–
以上のことから、高齢者を対象としたデイサービスやデイケアなどの介護現場においても、片脚立位の評価が活用されることが多くなっています。
▼片脚立位とともに測定することの多い「TUG」の評価方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
| 【関連記事】TUG評価のカットオフ値とは|評価初心者でも分かる測定方法TUGの評価で知っておきたい評価方法とカットオフ値(基準値)をご紹介します。 |
▶科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!

片脚立位の評価は、運動器不安定症のリスクや転倒のリスクを判断するために活用されますが、これらを判断するための指標となるカットオフ値をご存知でしょうか?
▶科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
片脚立位は、簡易的に測定できるため高齢者の身体機能の評価として幅広く活用されています。そのためカットオフ値や平均値も様々なものが公表されています。そのなかでも、リハビリテーションの専門家でもある理学療法士・作業療法士の評価の指標として、よく活用されている片脚立位のカットオフ値です。
合わせて片脚立位の年齢別の基準値もご紹介します。片脚立位の目標数値として参考にしてください。

では、実際に片脚立位の測定方法をご紹介します。
▶科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!

片脚立位の評価をする場合は、以下の物品を準備することですぐに検査を始めることができます。
【片脚立位で準備するもの】

片脚立位テストを行う場合は、以下の点に注意して測定するようにしましょう。
【片脚立位の注意点】

片足立位テスト以外にも高齢者の転倒リスクを判断する方法は様々あります。転倒リスクに関与するバランス評価を紹介します。
【転倒リスクの評価】
| (1)Functional Reachテスト測定方法は、足を肩幅に揃えて腕を肩関節90度挙げます。足を前に出すことなく、中指を目安に最大限にリーチした距離を測定します。3回テストを行い、最後の2回の平均値を求めます。 【カットオフ値】 ⑴虚弱高齢者の場合は、18.5cm未満は転倒リスクが高い (参考論文:Thomas et al., Arch Phys Med Rehabil. 2005) ⑵脳卒中片麻痺患者の場合は、15cm未満で転倒リスクが高い (参考論文:Acar & Karats, Gait Posture 2010) ⑶パーキンソン病患者の場合は、31.75cm未満で転倒リスクが高い (参考論文:Dibble & Lange, J Neurol Phys There 2006)などと報告されています。 |
| (2)BBS(Berg balance Scale)バランス能力や協調性、筋力、持久力、柔軟性、感覚など複合的な要素を測定するため、立ち上がりや360°方向転換などの14項目から測定します。 【カットオフ値】 最大スコア(56点) 0-20点:バランス障害あり 21-40点:許容範囲のバランス能力 41-56点:良好なバランス能力 |
| (3)TUGテスト(Time UP&Goテスト)測定方法は、椅子に深く座った状態で開始し、椅子から立ち上がり、無理のない早さで歩き、3m先の目標物を回って椅子に座るまでに要する時間を測定します。 ⑴13.5秒以上:転倒リスクが予測される ⑵30秒以上:日起居動作や日常生活動作に介助を要す ⑶11秒以上:運動器不安定症を判断する基準として、 (参考:公益社団法人 日本整形外科学会 運動器不安定症の定義と診断基準) |
▼転倒リスクを判断するバランス評価について詳しく知りたい方はこちらの記事がオススメです。
| 【関連記事】 バランス評価とは 転倒リスクを判断する評価方法についてご紹介します。 |

ご高齢者の転倒の原因には様々な要因があり、一人ひとりによっても異なります。そのため、片脚立位テストやファンクショナルリーチテストなど様々な評価を組み合わせて転倒リスクを把握した後に、その要因に合わせた転倒予防に取り組んでいく必要があります。
ご高齢者の転倒予防に効果的な方法は、集団や個別での「運動」とされています。特に「複合要素のプログラム」が転倒予防に有効です!
【転倒予防の種類】
▼ご高齢者の転倒の原因から転倒予防の方法を下記の記事で詳しく解説しています。評価の方法を学んだ後は転倒予防の方法も学んでみませんか?
| 【関連記事】 高齢者の転倒予防の基礎知識 転倒の原因から体操方法まで徹底解説します。 |
片脚立位は、バランス検査の1つとして「転倒リスク」や「運動器不安定症」を判断する評価方法です。転倒の要因やリスクは1つの評価だけで確定できるものではありません。様々な検査方法を組み合わせて高齢者の転倒予防に努めていきましょう。
リハプランでは、医療や介護現場で活用できる身体機能評価について詳しくご紹介しています。ぜひその他の測定方法についても学んでみてください。
デイサービス運営において必要な「評価・測定」について、一挙にまとめていますので、必要に応じて活用していただければと思います。
→→ 【完全保存版】デイサービスで活用できる評価・測定に関する記事まとめ|随時更新
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

機能訓練
コラム
2024/04/11

機能訓練
2024/04/10

機能訓練
2024/04/10
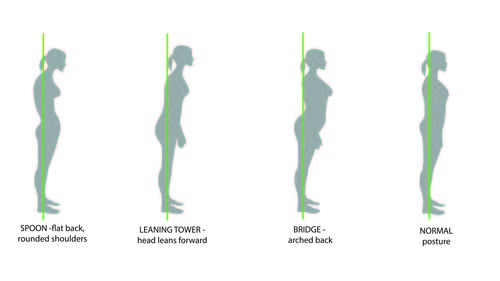
機能訓練
2024/04/09

機能訓練
2024/04/09

機能訓練
2024/04/09