【保存版】デイサービスの生活相談員の仕事内容 業務に役立つ情報まとめ
現場ノウハウ
2024/04/25
現場ノウハウ
お役立ち情報
更新日:2024/04/09
介護施設に寄せられるクレーム・苦情の対応に困っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、デイサービスをはじめとした介護施設での対応事例を紹介し、研修やマニュアルに使えそうな内容を掲載しました。 また、クレーム・苦情の種類に合わせた聴き方やテクニック・円滑なクレーム処理方法を「7つのテクニック」として解説しています。
▶科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!

介護や医療の分野では、「クレーム」「苦情」という言葉について正式な定義はありません。この記事では、介護・医療分野におけるクレームや苦情という言葉の違いを定義立てて、対応方法を解説しています。
▶介護サービスの質向上を実現するなら科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド)」
クレームとは、期待した水準のサービスが得られなかった時に、金銭や機能、サービス品質など実質的な補償を求めることです。クレームのきっかけとなった事案はいろいろですが、要求は、例えば「事前に説明されたサービス内容と違うから返金してほしい」や「もっと高品質のサービスを提供してほしい」などの実質的な補償や賠償の要求につながるものです。
苦情とは、サービスを受けることにより満たされると期待していた、大切にしてもらっていると感じる愛情や、気持ちや考えを尊重してもらえると期待してた尊厳欲求など、心理的な欲求が満たされなかった時に発生するものです。
苦情のきっかけの事案はいろいろありますが、要求は「丁寧にしてほしい」「わかりやすくしてほしい」「もっと優しくしてほしい」「気持ち良い態度にしてほしい」「早くしてほしい」など、気持ちの問題を埋め合わせしてほしい、もう不快な思いをしないように改善してほしいという要求につながる建設的なものが多いです。
クレームや苦情は、得られていない欲求を満たすために起こしている行動であるという側面を考えて対応することが大切です。

クレームには色々な種類がありますが、苦情や要望を言う人の欲求や要求から内容を整理すると、以下のような4つに分類できます。
また、クレームや苦情のきっかけとなる事案には以下のような4種類があります。
介護や医療などの仕事では、患者や利用者に対して治療、介護、看護、対応などのサービスを提供します。それぞれ一生懸命に相手に向き合っても、相手から見たら不十分・不満足という点があるかもしれません。
クレームや苦情をお聞きするのは辛いことですが、業務や対応改善のきっかけを提供してくれているかもしれない、原因は自分たちにあるかもしれないということを考えながら、仕事としてうかがうことが重要です。
仮に苦情の対象が自分には無関係な同僚の対応のことなどだとしても、自分が組織の代表で対応しているという気持ちで同僚を思いやることも大切です。そのような対応が、お相手の気持ちを鎮めるかもしれませんし、丁寧に対応することでおおごとにならずに済むかもしれません。
良いクレーム対応は、施設や病院のイメージを逆にアップさせる要因にもなりえるのです。
▶介護サービスの質向上を実現するなら科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド)」
介護施設、病院での苦情・クレーム対応研修では、接遇面を含めて相手に不快感を与えないためのチェックポイントや、実際に苦情を伝える役、苦情を受け付ける役に分かれてシミュレーションを行うなどの研修があります。
苦情やクレームを訴えている方は、興奮していることが多いので、クレーム苦情対応時には言葉遣いや態度、身だしなみなどの接遇マナー面には細心の注意が必要です。

クレーム対応の具体的な技術・テクニックについては、7つのポイントを抑えて進める方法をお伝えします。
▶介護サービスの質向上を実現するなら科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド)」
クレームや苦情は、この記事で紹介してきたような欲求が相手にあり、期待に満たなかったその欲求を叶えるために行動に出ている状態です。
相手の訴えはいろいろあると思いますが、繰り返し話していることや回りくどく言っていることの奥にある欲求を把握して、どうしたら満足してもらえるかを考えていきます。
なお、この最初の聞き取りではできるだけ初期対応者が対応し、すぐに責任者が出て行かないこともテクニック的には大切です。
解決する場合もなくはないですが、すぐに最終責任者が対応してしまうと、対応がうまくいかなかった場合にどのように落とし所を見つけていくかの選択肢が狭まるためです。
クレームや苦情では、相手からのお詫びの言葉を求めることが多いですが、クレームや苦情になった事案そのものについては即座に謝罪やお詫びをするべきではありません。
しかし、お詫びの言葉をクッション言葉として次につなげることはできます。
例を挙げるとすれば、「すぐに不満の気持ちに気付けずに、お話をお聞きするのが遅くなって申し訳ありませんでした」というお詫び言葉を添えることが有効です。相手は不満や不安が溜まってしまい、とうとうアクションに移してしまったという状態がほとんどです。
その前にお気持ちの変化に気づくことができなくて申し訳ないとお詫びすることは、接遇的な観点からも良い対応です。
介護や医療の仕事の基本的な姿勢として傾聴が重要視されているとおり、クレーム対応や苦情の聞き取りでも最後まで話をよく聞くことが最も大切な姿勢です。
途中で話を遮らずに相手が「話し切った、言いたいことはすべて伝えた」と思える程度にしっかりと聞き取りを行いましょう。
苦情・クレームを伝えてくる人は、とにかく「伝えたい」「全部知ってほしい」と思っているものです。事実を把握し正しくジャッジするという面からも、傾聴に徹して相手の言い分をすべて受け取ることはとても大切なテクニックといえるでしょう。
接遇や基本的なマナーとして、相手が話しているときに割り込まないのは多くの人が意識しているでしょう。しかし、自分にとって理不尽な訴えを一方的にされていたり、相手が完全に誤解していたり、侮辱的な発言をされたりすると割り込んで否定したくなると思います。
相手が興奮してクレームや苦情を言っているときには、特に汚い言葉や関係のない話しなどまでいろいろ話してくることもあります。しかし、クレーム対応テクニックとしては、とにかく話に割り込まないことが重要です。
相手が興奮して誤解したまま訴えたり、侮辱的な発言などまで含んでいるときは落ち着いて全て聞き、特にその日は答えなどは出さず、持ち帰りましょう。
クレーマーと言われるような人は、ボイスレコーダーで録音し、言い返したり、喧嘩口調になったりした部分だけを切り取って違った訴えに発展させたり、悪い評判などを広める材料に使ったりするケースもあります。
辛いですがグッとこらえて、相手の訴えや要求の内容と合わせて不適切な発言などもこっそりメモしておき、傾聴している姿勢でいましょう。
相手の話について一通り傾聴し、相手の興奮や感情が静まったところで、話の内容を整理していきます。それに合わせ、自分に答えられる範囲で自分たちの立場、自分たちの事情などを説明し、合理的に相手の同意や納得感を確かめていきましょう。
介護や医療の分野では、関係性が崩れてしまっている場合や、悪質な場合を除けば、施設側の立場や事情について伝えることで難しさなどに理解を示そうとしてくださる方もいます。
同情を誘うわけではなく、今の状態について説明した上で、相手の要望にもできるだけ答えていくという姿勢を示すことで、クレームや苦情の落とし所を考えやすくなり、まとめやすくなるでしょう。
クレームや苦情は業務改善やサービス品質向上のきっかけにもなるというお話をしましたが、ほとんどの場合苦情やクレームを言ってくる方は、要望を伝えれば施設や病院は応えてくれると考え、アドバイスや指導という意味合いも込めている場合が多いです。
得るものが少しでもあったら「業務改善やサービス品質向上の気付きのきっかけを与えてくださりありがとうございます」というニュアンスのことを伝えます。
また、一方的で到底寄り添えない要望の場合には、「お気持ちの変化に気付けず、お話をお聞きするまでお時間をいただいき申し訳ありませんでした」というお詫びの言葉を再度伝え、精一杯の誠意を示しましょう。
施設や病院ではクレーム報告書や苦情対応票などの記録様式を定め、担当者や責任者に提出共有する方式をとっていることが多いです。ひととおり聞き取りが終わった後は、それに則った対応を進めていきましょう。
介護や医療のクレーム・苦情には、実質的な保証を求めるクレームと、心理的な埋め合わせを求める苦情があります。聞き取ったクレーム・苦情がどちらにあたるのかをしっかり見極めるのも大切です。
訴えの言葉や内容、自分の対応などを的確に伝えて引き継ぎ、共有していきましょう。
介護保険サービスの事業所には、運営基準上「利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。」という法律上の苦情窓口の設定義務があります。
この苦情相談窓口は、事業所の中で苦情対応責任者を選任することや、区市町村の窓口、国保連合会や保険組合などの保険者に関わる窓口などを、重要事項説明書などで利用者や家族に説明する必要があります。
もっとも大切なことは普段から行うべき接遇マナーの内容です。また、苦情やクレームの内容を的確に伝達していくために、施設や病院ごとに定めている苦情対応フローや、クレーム対応記録、お客様や利用者からの声を取り入れた例などを、誰もがわかるように共有することが大切です。
介護の接遇マナーについてもっと詳しく学びたい方は以下の記事などもあるので、ぜひご一読ください。
▶︎社会人としての 敬語の使い方 や 言葉遣いの問題 介護の接遇マナー
▶︎介護の接遇マナー向上 挨拶の仕方やお辞儀で好印象を与える方法
▶︎介護の接遇マナー向上 身だしなみ(外見)で第一印象をアップさせる方法
▶︎介護職員の接遇とは おもてなしの心を表現する4つのポイント【基礎知識】
▶︎ホスピタリティとは 接遇マナーとの違いから事例まで
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

現場ノウハウ
2024/04/25

現場ノウハウ
2024/04/25

現場ノウハウ
2024/04/25
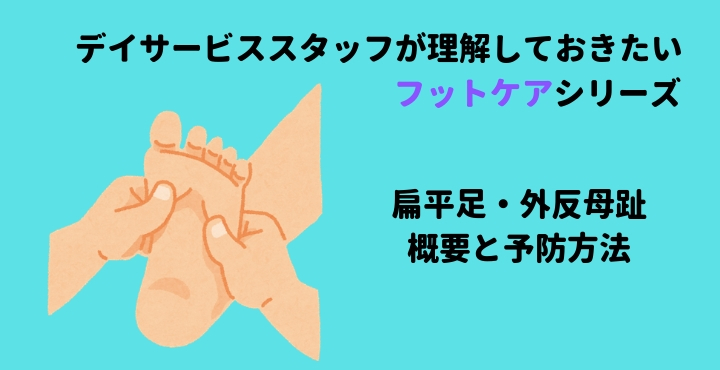
現場ノウハウ
2024/04/25
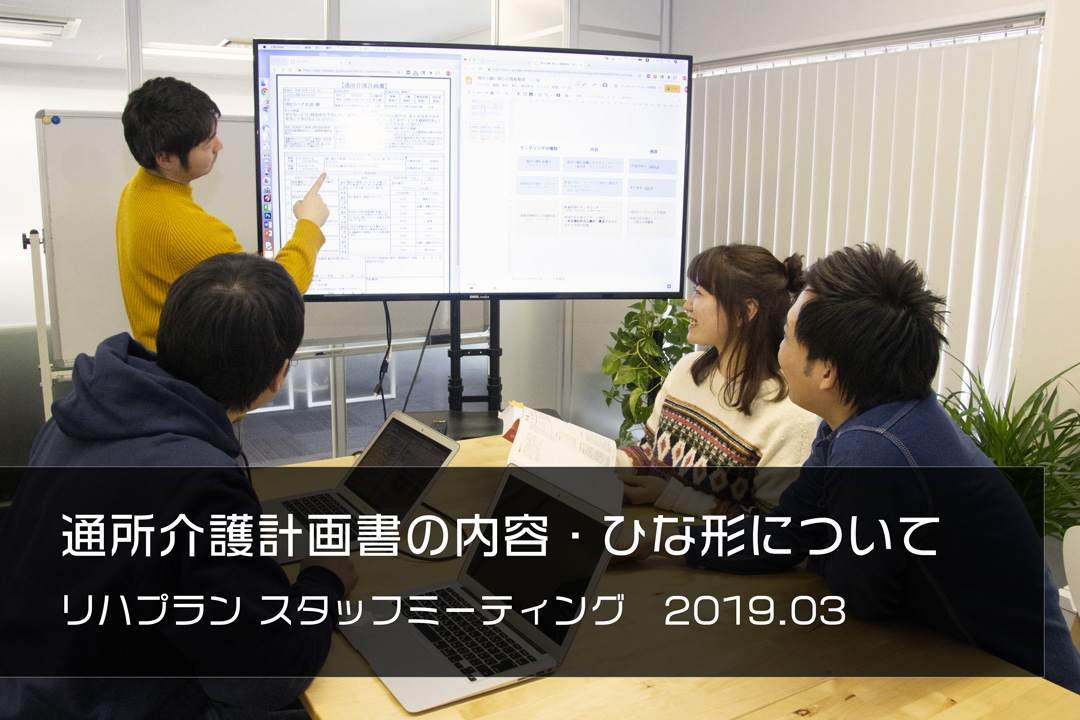
現場ノウハウ
2024/04/25

現場ノウハウ
2024/04/25