介護のアセスメントとは?目的や重要性・書き方のコツやポイントを紹介
コラム
2024/04/19
コラム
介護スタッフの基礎知識
更新日:2023/08/02
介護現場では、相手の自尊心を尊重した正しい言葉遣いが求められます。敬語の適切な使い方に加えて、過剰敬語を避けることや高齢者を子供扱いする声がけなどに気を付けましょう。この記事では、接遇マナーの向上に役立つ具体的なポイントを紹介します。
→科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
→無料研修会「ついに始まる2024年度介護報酬改定 全貌を一気に解説!」
この記事の目次
施設やデイサービスなどの介護現場では、相手に対して正しい言葉遣いをすることが重要視されています。
高齢者や要支援者の方々は、身体的な制約や認知機能の変化によって困難を抱えていることが少なくありません。
医療・介護現場で働くスタッフは、そのような方々に寄り添い、思いやりのあるコミュニケーションをとることが求められます。
正しい言葉遣いには、丁寧な敬語の使用や尊重の意を示す言葉遣いが含まれます。
また、相手の立場や気持ちに寄り添いながらコミュニケーションをとることはいかなる場面でも欠かせません。
適切な言葉遣いと態度で接することによって、信頼関係を築き、利用者の尊厳と自尊心を守ることにつながります。
利用者の方々が心地よく過ごせるよう、お互いに思いやりと配慮を持ったコミュニケーションを心掛けましょう。
相手に対して適切な敬語を使うことは、接遇マナー向上に欠かせません。
敬語には、丁寧語、尊敬語、謙譲語の3種類があります。
それぞれの違いを理解し、状況や相手に合わせて使い分けをしましょう。
以下に敬語の種類と正しい使い方の例を挙げて説明しますので、ご参考ください。
尊敬語とは、相手への敬意や尊敬の気持ちを表すために使われる言葉遣いの一種です。尊敬語は相手の地位や年齢、経験などによって使用され、相手を敬う意図があります。
介護や医療の現場では、利用者や患者さんへの丁寧な対応が求められるため、尊敬語の適切な使い方を身につけることが重要です。
尊敬語を上手に使うことで、相手への敬意や尊重の気持ちを表現し、信頼関係を築くことにつながることでしょう。
【尊敬語の使い方の例】
普通の言い方:見る
尊敬語の場合:ご覧になる
普通の言い方:言う
尊敬語の場合:おっしゃる
普通の言い方:食べる
尊敬語の場合:召し上がる
謙譲語とは、自分自身の行為や身分を謙遜し、相手を尊重するために用いられる言葉遣いの一種です。自分が行うべきであることや自分の立場に関わることについて謙遜し、相手を重んじる意図があります。
謙譲語は、日本の社会文化において上司や年上の方、尊敬される存在に対して使われることが一般的です。敬語の中でも最大級の表現であるため、少々堅苦しい印象を与えてしまう可能性は否めません。
介護現場では、特に会議や対外活動などのかしこまった席で使用するのが適切でしょう。
【謙譲語の使い方の例】
普通の言い方:食べる
謙譲語の場合:いただく
普通の言い方:する
謙譲語の場合:させていただく
普通の言い方:行く
謙譲語の場合:伺う
丁寧語とは、相手への敬意や丁寧さを表現するために用いられる言葉遣いの一種です。主に目上の人や知人などに対して使用され、丁寧さや礼儀を重んじる意図が込められています。
丁寧語は、敬語の中では最も堅苦しい表現をせずに柔らかい表現で伝えることができるため、介護現場で活用しやすい敬語です。
うまく活用すれば相手に対する敬意や配慮の気持ちを柔軟に示すことができ、円滑なコミュニケーションにつながることでしょう。
【丁寧語の使い方の例】
普通の言い方:わかりました
丁寧語の場合:かしこまりました、承知しました
普通の言い方:できません
丁寧語の場合:私にはできかねます
普通の言い方:だれですか
丁寧語の場合:失礼ですがどなた様でいらっしゃいますか
二重敬語とは、一つの語について尊敬表現を重ねて使ってしまう言葉遣いのことです。
例えば、目上の人が「話す」ということを丁寧に伝えようとした時に「お話になられる」と表現したとしましょう。この場合「お」と「なられる」の2つの尊敬表現が入っています。
また、過剰敬語とは、敬意の対象を誤って尊敬表現を設けてしまっている言葉遣いのことです。
例えば「○○様のお車のお具合が悪い」など、相手の所有物までも高めてしまう表現は不自然であり過剰敬語となります。
介護現場では、敬語が基本ではありますが、過剰な敬語や二重敬語は相手に不快感を与えかねません。
下記に二重敬語と過剰敬語の例を記載しましたので、ご参考ください。
「来ました」の場合
二重敬語:おいでになられました
正しい表現:みえました、おいでになりました、いらっしゃいました
「食べますか?」の場合
二重敬語:お召し上がられますか?
正しい表現:召し上がりますか?
「見ました」の場合
二重敬語:ご覧になられました
正しい表現:ご覧になりました
【過剰敬語の例】
過剰敬語:ご利用者様の車椅子が故障なさった。
正しい表現:ご利用者様の車椅子が故障した。
過剰敬語:そちらは雨が降っていらっしゃる。
正しい表現:そちらは雨が降っている。
介護の現場においては必ずしも敬語のみが正解ともいえない場面が多く存在します。
敬語を使った言葉は長くなりやすく、わかりやすさの欠如が生まれやすいためコミュニケーションが円滑に進まない恐れがあります。
そのような場面では、丁寧さを重視した敬語ではなく、相手に伝わりやすい言葉を選ぶことも大切です。
認知症の方への対応では、認知症に伴う認知機能低下に配慮が必要です。以下に親しみやすい話し方について、5つのポイントをあげましたのでご参考ください。
認知症の方は、ご自身が話したり聞いたことを忘れてしまうこともありますが、感情は長時間保たれるとされています。その中でも、悪い感情が残りやすいとされています。
優しく接してくれる相手には穏やかな感情を抱きます。認知症の方への声かけでは、時に通常の介護場面のような説明や丁寧さを重視した声がけよりも、相手に共感する気持ちで状況に合わせた対応をする方が良いこともあるでしょう。
介護職にふさわしい言葉遣いのチェックリスト
言葉遣いについては意識するべき点が多く、 すぐに理解して上手く活用することは簡単ではないかもしれませんが、大切なことです。また、普段の言葉遣いを見直すきっかけとして以下にチェックリストを作成しましたので、ご参考ください。
シチュエーションや相手によって、適切な言葉遣いは異なってきますが、ここでは言葉遣いの「基本」のチェックリストをまとめました。
日々のご自身の言葉遣いを振り返りながら、基本のチェックリストを抑えた言葉遣いが行えるようにしましょう。
【基本的な言葉遣いのチェックリスト】
⬜︎正しい敬語の使い分けができているか
⬜︎馴れ馴れしいタメ口を使っていないか
⬜︎あだ名や呼び捨てをしていないか
⬜︎子供扱いする言葉遣いを使っていないか
⬜︎命令口調になっていないか
⬜︎敬語を意識しすぎてよそよそしい口調になっていないか
⬜︎「〜してあげる」という上から目線の言葉遣いになっていないか
⬜︎高齢者が理解できない若者言葉や専門用語を使っていないか
挨拶や返事は「するかしないか」ではなく「どのようにするか」が重要です。日々の会話での言葉遣い以上に、挨拶では表情やからだを使った非言語的な表現も大切なポイントといえるでしょう。
【挨拶のチェックリスト】
⬜︎元気よく声をかけられているか
⬜︎明るい声のトーンで、親しみやすい雰囲気づくりに努めているか
⬜︎目線の高さを合わせているか
⬜︎明るい表情や笑顔でいるか
⬜︎相手が話している際は大きく頷き、共感の姿勢を示す
介護サービスの利用者は認知機能が低下している方も少なくありません。要介護・要支援状態にある方は、身の回りの動作を行う際に、サポートを必要とします。
しかし、そのような場面で、利用者を否定したり、ないがしろにするような言葉を使うのは避けましょう。
介護現場では、特に介助中の拒否や協力がうまく得られないときに、職員は焦りから強い命令口調になってしまいがちです。忙しいときこそ心に余裕を持ち、ご利用者ひとりひとりに配慮した言葉遣いを意識しましょう。
【利用者に向けて使ってはいけない言葉】
・不安にさせる言葉:「家族に言いつけますよ」
脅したり、強制するような言葉はかけないこと。
・焦らせる言葉:「早くして」「できないんだからやらないでください」
動作が遅くても急かさないこと。
・責める言葉:「おかしいですよ」「何度言ってもできないんですね」
利用者が間違えたことを話したり、行動をとっても強く指摘しないこと。
・否定する言葉:「間違っていますよ」「何を言ってるかわからないよ」
利用者が事実と違う内容を話していても、頭ごなしに否定する言葉はかけないこと。
業務に追われている忙しい時間帯に、家族対応しなければならない状況で、つい返答が雑になってしまうことは少なくありません。
しかし、多くの不安を抱きながら介護を行なっているご家族が、介護現場の職員にぞんざいな対応をされたらどのような感情になるでしょうか。
家族対応に誠実さがない場合、相手は不信感がつのりクレームへと直結してしまいます。ご家族への適切な対応も、より良い介護サービスの提供のためには欠かせません。
【ご家族向けに使ってはいけない言葉】
・適当な返答:「あー、はいはい」「ちょっと待ってねー」
ご家族から声を掛けられた際、適当な返事はしない。
・他人行儀なぞんざいな返答:「知りません」「私に聞かれても、、」
ご家族からの質問や要望があった場合に、ぞんざいな対応をしないこと。
・冷たい返事:「よくわかりません」「こんなのたいしたことないんで」
ご家族がご利用者様の体調の異変や外傷に気付いた際に、関心の無いような冷たい返事は避けること。
・カっとなって反論しないこと:「こっちも忙しい中でやっている」
ご家族から指摘やクレームを受けた際に、反射的に反論しないこと。
同僚との会話では、ついくだけた口調になってしまいがちです。しかし、相手の気持ちを尊重せずに、適切な言葉遣いを全く意識していないと、関係性が悪くなることにもつながりかねません。
共に働く同僚同士が尊重し合えていない場合、提供する介護の質が低下する可能性があります。気持ちよく働ける良い雰囲気づくりのためにも、利用者だけではなく同僚にも適切な礼儀をもって接しましょう。
【同僚に使ってはいけない言葉】
・人をバカにする内容や悪口:「あの人はどうせわからないわよ」
同僚同士で利用者をバカにするようなことや悪口は言わないこと。
・相手を見下すような表現:「こんなこともわからないの?」「この仕事向いてないよ」
若手や新人の介護職員を下したり、尊厳を傷つけるような言葉は使わないこと。
・強い命令口調:「早くやっといてよ」
同僚に命令したり、強い口調で威圧しないこと。
・無視:「・・・・」
相手からの挨拶や声がけを無視しないこと。
介護現場で利用者を相手にお話をする場合には、基本的には敬語を使うことをおすすめします。敬語は目上の方への敬意を示すためだけでなく、思いやりやおもてなしとしての大切な意味を持っています。
複雑な敬語を使うのは日本の特徴です。しかし、一期一会と言う言葉があるように、相手との人間関係を丁寧に・大切に構築する上では、敬語という表現方法はとても重要なものです。
丁寧語、尊敬語、謙譲語などの複数の表現方法の適切な使い分けに加え、二重敬語や過剰敬語を避けることも大事なポイントです。
敬意と自然なコミュニケーションを通じて、利用者との信頼関係を築き、より良い介護サービスの提供につなげましょう。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

コラム
2024/04/19

コラム
2024/04/18

コラム
2024/04/18

コラム
2024/04/18

コラム
2024/04/18
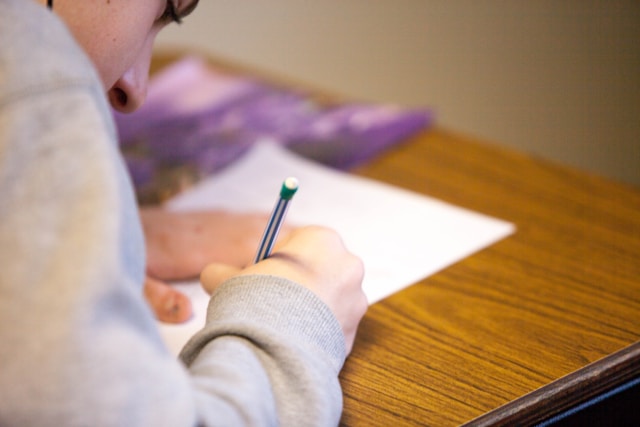
コラム
2024/04/17