「介護×ICT」で現場はどう変わる?メリットと導入事例・今後の展望
運営ノウハウ
2024/04/18
運営ノウハウ
リスクマネジメント
更新日:2024/04/09
リスクマネジメントとは、介護事故のリスクを把握し、組織的に管理することで事故を未然に防ぐことを目的とした活動です。介護現場での事故や事件、ヒヤリハットやトラブルは一生懸命に働いていると必ず起こってしまい、事故を起こしたスタッフは利用者様の安否を想い心が苦しくなります。そこで今回は、介護スタッフ向けにリスクマネジメントの研修資料から重要な取り組み方を4つのステップに分けてまとめてご紹介します。
→科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
→無料研修会「ついに始まる2024年度介護報酬改定 全貌を一気に解説!」
この記事の目次
▶科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
介護現場におけるリスクマネジメントとは、介護事故のリスクを把握し、組織的に管理することで事故を未然に防ぐことを目的とした活動です。
利用者の「安心・安全」を守るためにも、介護事業所の信用を高めるためにも、運営上必須の課題です。そこで本稿では、介護現場向けのリスクマネジメントの基本的な考え方からご紹介します。
▶介護サービスの質向上を実現するなら科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド)」
介護現場でのリスクマネジメントは、利用者やご家族に良質な介護サービスを提供するために大切なものです。また、スタッフを守り、安心して働ける職場環境を作るためにも必要になるでしょう。
介護現場におけるリスクマネジメントの目的は以下の3つが挙げられます。
以下に詳しく解説しますのでご参考ください。
利用者の安全を確保し、安心してサービスを利用するためには、リスクマネジメントが欠かせません。
介護サービスの利用者は、加齢や疾患などにより、身体機能が低下しているケースが少なくありません。
そのため、些細なことでも大きなケガにつながりやすい状態です。事故やケガのリスクが多い介護事業所では、利用者を守るため、それらを予防するリスクマネジメントが大切になります。
リスクマネジメントは利用者だけでなく、スタッフの働く環境にも影響します。
介護事故は職員のメンタルに大きな負担となる可能性があり、起きてしまった場合には自責の念にかられる方もいるでしょう。
介護事故の原因として、福祉用具の不備やスタッフの人数不足など、環境面が影響している可能性も十分に考えられます。
適切なリスクマネジメントをし、環境を整えることで、介護事故を未然に防ぐことができます。
介護事故によって、家族から訴訟を起こされるケースがあります。過去には事業所の責任を問われ、高額な賠償金の支払いを命じられる事例も実際にありました。
リスクマネジメントを行い適切なケアを提供することで、訴訟を起こされる可能性を減らしましょう。
訴訟を起こされると事業所の信頼が崩れることにもつながりかねません。信頼の喪失は、介護事業所の運営に大きなダメージを与えます。
適切なリスクマネジメントを行うことで、訴訟への発展を防げます。
介護事業所でのリスクマネジメントは、なぜ重要なのでしょうか?
介護サービスの利用者のほとんどは高齢者ですから、年を重ねるごとにどうしても心身の変化(機能の低下)は起こります。その影響で免疫力が低下すると病気にかかりやすくなりますし、バランス機能が低下すると転倒を引き起こすこともあります。
まずは高齢者の心身の状態の変化について整理してみましょう。
《高齢者の身体の変化》
《高齢者のこころの変化》
以上のような変化によって、事故の危険性も高まります。実際に介護現場での事故発生状況としては、圧倒的に「高齢者の転倒」が多く、一度の転倒によって「骨折」につながるケースもあります。骨折は予後のADLを低下させるだけでなく、QOL自体も下げてしまうこともあるので、介護職員は転倒予防に留意して接することが重要となります。
想定される事故を見つけ出し、どのような場面で起きやすいのかを理解し、対策方法をスタッフで共有するといった、リスクマネジメントの取り組みが非常に重要になるのです。
ここでは介護現場で頻繁に目にする事故について、事例を用いて説明します。
▶介護サービスの質向上を実現するなら科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド)」
ベッドやトイレから車いすへの移乗は、身体機能が低下した高齢者にとってバランスを崩し、転倒しやすい動きの1つです。
転倒は骨折や脳出血など重大な事故につながる可能性があるため、十分に注意する必要があるでしょう。
移乗時の転倒の要因として、車いすのブレーキの忘れなど、確認不足が挙げられます。その他に、体に合わない手すりの位置などの環境不備、利用者の認知機能の変化なども考えられる要因です。
以下に予防するための例を挙げましたので、ご参考下さい。
【予防のための一例】
身体機能の低下に伴い、飲み込みや吐き出す能力の低下がみられる場合があります。それらの影響による飲食時の誤嚥や窒息は命に関わるため、注意しなければなりません。
過去にスタッフが少し目を離した際に誤嚥し、訴訟事件に発展した事例も存在します。
誤嚥の要因として以下のケースが考えられます。
食事や飲水時の誤嚥を予防するためには以下のような対応が考えられるでしょう。
【予防のための一例】
利用者の薬の飲み忘れや飲み間違いも起こりやすい事故の1つです。要因として、服薬管理マニュアルが不十分、服薬時の確認不足、スタッフ間の連携不足などが挙げられるでしょう。
具体的には、以下のようなミスの例が挙げられます。
薬の飲み忘れと飲み間違いを予防するためには以下のような対応が考えられるでしょう。
【予防のための一例】
介護事故は多種多様であり、利用者の状態や環境要因など複数の要因が絡み、引き起こされます。全ての介護事故が、個人の注意で予防できるとは限りません。
適切に介護事故を予防するためには、組織でリスクマネジメントを強化し、事前に事故の対策をする必要があります。
リスクマネジメントを強化するためには、事故が起きる危険性を把握してマニュアルを作り、運用することが大切です。
ここではリスクマネジメントを強化するための4ステップを紹介します。
リスクマネジメントの最初のステップは、リスクの特定・発見・把握です。
まず、施設や事業所内で利用者に危害を与える可能性について検討します。現場で挙げられたヒヤリハットや事故事例の報告を参考にするとよいでしょう。
ヒヤリ・ハットとは、事故に至らなかったが、事故に直結してもおかしくない「ミス」や「冷やり」「ハッ」としたことを指します。
1件の大きな事故の裏には29件の軽微な事故、そして300件のヒヤリハットがあるとされており、ヒヤリ・ハットを把握することがリスクマネジメントにおいて重要になります。
リスクマネジメントは「防げる範囲」と「防げない範囲」に分けることが重要です。
リスクマネジメントでは防げる範囲に焦点を当てて、分析や対応策を検討します。最初のステップでリスクを見つけ、防げる範囲を定めることが重要です。
加齢や疾患に伴う身体機能の低下による歩行中の転倒や飲食での誤嚥など、避けられないリスクは多くあります。防げない事故に対して、過度に対策を行なった場合、次のような問題が生じるかもしれません。
たとえば、転倒リスクがあるから「一人で立たせない」「歩かせない」という対策を実施したと仮定した場合、利用者の行動制限と身体拘束を行うことになってしまいます。
身体拘束は虐待に当たると考えられ、緊急でやむを得ない場合を除いて原則禁止されています。
しかし、対策ができないということではありません。見守り機器などを適切に活用することで、危険な単独行動を早めに察知する対策をとることは可能でしょう。
つまり、防げない事故の範囲は存在しますが、リスクマネジメントによって防げる範囲を定めることでリスクを軽減することができます。
リスクを発見した次のステップは、事故事例の分析と評価です。
「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」「なぜ」といった項目で、事故が起きた状況を把握しましょう。
事故の全体像がみえると、対応するべき課題がわかりやすくなります。また、事故状況を把握したあとは分析する必要があります。
分析する際は、4Mというフレームワークを利用します。
4Mは原因分析や対策検討の際に人的要因(Man)、設備的要因(Machine)、作業環境的要因(media)、管理的要因(Management)の4つの視点(4M)から要因を抽出し整理するフレームワークです。
先入観を排除し、原因の本質を確実にとらえられるのが4Mの特徴です。
フレームワークに沿って以下の4つの要因に分けて検討しましょう。
以下に、要件分析の例を挙げます。
【事例】入浴介助中に浴室内で滑って転倒してしまった
【要因分析】
| 人的要因 | 職員が事前に床面の確認をしていなかった介助位置が遠く、介助方法も不十分であった利用者は目が悪く足元が確認できなかった |
|---|---|
| 設備的要因 | 浴室の床面の水が流れにくかったシャワーが届かず流せない場所であった |
| 環境要因 | 職員の人数が不足していた一度に多くの利用者が使用していた |
| 管理的要因 | 介助する担当職員が決まっていなかった浴室を流すなどのルールが決まっていなかった |
上記の4つの視点に分けることで問題が明確になり、具体的な対策を検討しやすくなります。
事故の要因を分析した後、具体的な対応策を検討します。
対応策は、施設内での事故防止マニュアルの作成や環境整備などが挙げられます。要因分析をもとに具体的な対策案を挙げることが重要になるでしょう。
たとえば、入浴介助中に浴室内で滑って転倒してしまった事例を想定すると、以下のような対策案が挙げられます。
浴室の環境整備や浴室利用のルールをマニュアルとして整備することが、浴室での転倒予防策になります。また、作成したマニュアルを職員研修などで施設全体に共有することも重要です。
「職員が気をつける」などの対策案は具体的ではないため、組織全体で共有できる対策案を考えましょう。
対策案を考える注意点として、利用者の尊厳を守ることが基本となります。安易な身体拘束や行動を制限する対策は不適切です。利用者の負担が少なく、安全にサービスが利用できるような対応策を検討する必要があります。
リスク管理マニュアルを1から作成する場合は、厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」が参考になります。
参照:厚生労働省 平成25年「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」(平成29年6月23日アクセス)
リスクマネジメント強化の最後のステップは、対応策を周知して運用することです。
マニュアルを作成したのであれば、職員研修や回覧するなど、職員全体で内容が共有できるよう周知に取り組みましょう。
マニュアルが周知され、業務に取り込まれて運用されることで、ようやく適切な事故防止対応ができます。
しかし、マニュアルの周知や運用は容易ではありません。マニュアルを周知して運用するためには、時間をかける必要があります。
対策案の周知や運用を定着させるために「安全管理委員会」の設置は有効的です。
安全管理委員会は組織全体の中心となり、リスクマネジメントを行い、対策案の周知や運用を働きかける役割を持ちます。
安全管理委員会の設置によって定期的なリスクマネジメントに取り組める環境づくりが行いやすくなるでしょう。
■安全管理委員会の構成メンバー
部門、職種、職位など多職種でメンバー構成とすることで偏りがなく現場に即した実効性のある対策の議論、活動へとつながることが期待できます。
■安全管理委員会の実施内容
マニュアルを導入するだけでは、リスクマネジメントとして不十分です。情報を周知し、運用を徹底できるような工夫が重要です。
参照:東京都福祉保健局 平成21年「社会福祉施設におけるリスクマネジメントガイドライン」(平成29年6月23日アクセス)
ここまでリスクマネジメント強化の取り組みを4つのステップでご紹介しました。リスクマネジメントは実施するだけでなく、継続することが大切です。
介護の現場では、利用者の状態は日々変化し、それに伴いリスク対応も変わります。そのため、介護現場での事故防止には「継続的に取り組む仕組みづくり」と「報告しやすい雰囲気」が必要です。
継続的に取り組む仕組みづくりには、PDCAサイクルを用いて作成したマニュアルや設備などの定期的な見直しが有効でしょう。
PDCAとは、PLAN(目標設定)⇒ DO(実行)⇒ CHECK(検証)⇒ ACTION(目標の修正と実行)の手順を指します。
具体的には、介護現場のリスクマネジメントにおけるPDCAサイクルは以下のようになります。
このようにPDCAサイクルを回していくことで、定期的にリスクマネジメントを見直すことができます。
報告しやすい雰囲気づくりも介護現場における事故防止に有効です。
リスクマネジメントをする上では、リスクの特定が第一歩であり、そのためには事故やヒヤリハット・インシデントに関する職員からのスピーディな報告が必要です。
報告しやすい雰囲気をつくるためには、事業者や上司、スタッフ同士が普段からお互いの意見を聞く姿勢を持つことが大切になるでしょう。
また、リスクマネジメント研修などを活用して各職員に感想を聞くなど、日ごろから介護事故に関する意識を高めることも重要になります。
職員が意見を言いやすい雰囲気を作ることもリスクマネジメントの重要な要素の1つです。
リスクマネジメントは、利用者が安全にサービスを利用し、スタッフが安心して働くための重要な要素です。
リスクマネジメントの強化は「リスクの発見と特定」「分析」「対応策の立案」「組織全体への周知と徹底」の4ステップで実践できます。
しかし、4ステップのみでは十分にリスクマネジメントできません。スピーディで適切な対応をするためにも、継続的にリスクマネジメントに取り組めるような仕組みづくりや報告しやすい雰囲気づくりも大切です。
リスクマネジメントは事業所の運営や信頼に関わる重要なものです。今回の内容を参考にマニュアル作成や環境整備など、組織全体でリスク対策を図り、リスクマネジメントの強化に活用していただけたら幸いです。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

運営ノウハウ
2024/04/18
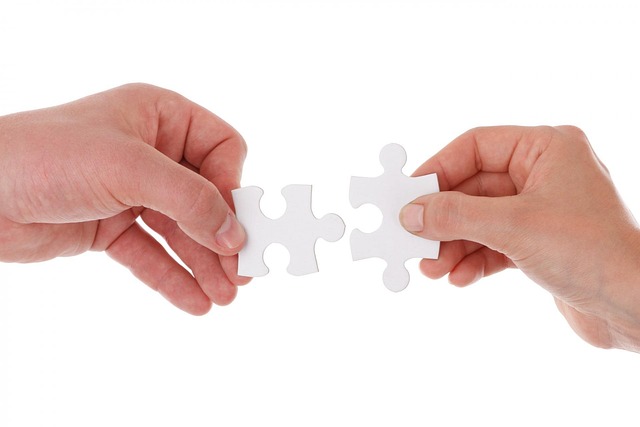
運営ノウハウ
2024/04/18

運営ノウハウ
2024/04/18

運営ノウハウ
2024/04/17

運営ノウハウ
2024/04/17

運営ノウハウ
2024/04/17