BMIの計算方法と標準値|高齢者の平均体重から分かる肥満や低体重
現場ノウハウ
2024/04/23
現場ノウハウ
お役立ち情報
更新日:2024/04/07
介護業界では「自立支援」が重視されています。自立支援を考えた時、デイサービスにおける機能訓練、機能訓練指導員の役割は非常に重要です。自立支援の考え方やアプローチ方法はご利用者一人一人の心身状況、ADL、健康状態、生活環境などを踏まえ、目標や支援方針が異なります。本来であれば一定以上のスキルや能力が担保される必要があります。この記事では、デイサービスにおける機能訓練のあり方について理学療法士が解説をしていきます。
→科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
→無料研修会「リハビリ支援ソフト「Rehab Cloud リハプラン」デモンストレーション会」
この記事の目次
現在のデイサービス運営において自立支援の視点が重要視されており、「機能訓練指導員」の役割は非常に大きいです。介護の今後は厚生労働省が「自立支援」を推し進めているからです。デイサービスでは、個別機能訓練加算の算定の有無にかかわらず、機能訓練指導員を配置することとなっています。
自立支援を達成するには、ご利用者一人一人の心身状況、ADL、健康状態、生活環境などを踏まえた上で、機能訓練やリハビリテーションの概念が必要だからです。
今回この記事では、デイサービスで機能訓練を行う必要性について現役の理学療法士が解説をしていきます。
自立の定義とは何かを考えてみたいと思います。
非常に捉え方が難しい概念だと思いますが、身体的に病気がないだけではなく、精神的かつ社会的に良好・安定した状態と考えると理解しやすいかもしれません。
自立の定義はありませんが、自立に近い概念として「健康」について、世界保健機構(WHO)はこのように定義づけています。
健康とは、肉体的、精神的および社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。
では、「自立支援介護」ということにフォーカスをあてて、さらにデイサービスが自立支援をしていくためにはどうしたらいいのかを考えてみると、機能訓練は切っても切れない関係にあります。
自立支援という言葉の定義は見つかりませんが、意味を簡単に表すと「自分に適した方法で生活することを支援する」というとわかりやすいかと思います。
自立支援は人やものに頼らず、自分でできることを増やすという意味合いも含みますが、頼らないことが最善だと考えるとそれはよくありません。
自立支援とは、その人にとって妥当な方法で、その人に合わせた支援を行なっていくことです。
自立支援介護について知りたい方は、こちらの記事で紹介していますのでぜひご一読ください。
▶︎自立支援介護とは|4つの基本ケア・自立支援の重要性と考え方
機能訓練という言葉を連想するとどうしても、筋力トレーニングや歩行訓練ということを考えがちです。
もう一度「自立」という言葉を考え直してみましょう。
自立のためには、身体面だけでなく「精神的かつ社会的にも安定した状態」が望ましいです。つまり、デイサービスでの機能訓練はただ単に運動をするだけでなく、精神的かつ社会的な要素も含めてサポートする必要があるということを理解してください。自立支援では、精神的、社会的な面まで健全を目指すために、具体的には、主な生活場所である「居宅」での家族との関係性や、疾患の苦痛、将来への不安など含めて支援していくということが大切です。
自立支援について考える時、どれくらい自立支援のためになったかということの効果を評価する方法がないかを考えます。
自立支援の評価を行う場合、非効率ではありますが、介入前にどの部分に課題があるかを明確にして、現在の状態を詳しく記録しておきます。例えば、トイレへの移乗についての自立支援に取り組む場合には、現在のトイレでの立ち上がりの状況・方向転換・手すりの捕まり方、どれくらい時間がかかるか、着座の様子などを記録しておき、気になる点を考察します。
その中で例えば離殿から立ち上がりにかけて介助が必要な状態だとしたら、その立ち上がりをどうすれば楽にできるのか方法を考えていきます。
自立支援について考える前ならば、おそらく脇を抱え上げる介助をしたり、膝のあたりを固定して持ち上げる介助を行うなど他力で介助する部分が多いと思いますが、立ち上がりについてさらに分解していくと、ちょっとお尻を浮かすところだけ介助すればできるかもしれませんし、手すりを持つ位置の声かけで楽に立ち上がれることに気付けるかもしれません。
そのためにはFIMやBirthel Index(バーセルインデックス)といったADL評価をして、ご利用者の全体像を把握していく必要があります。FIMやBIについては機能訓練指導員の方もどのように行ったらいいのか、どう評価したらいいのか非常に悩む部分があると思います。
この辺りの詳細についてはこのサイトでも数多くまとめていますので、合わせてお読みいただけたらと思います。
▶︎FIMとは|FIMの評価方法と点数付けで知っておきたい基礎知識【総論】
▶︎バーセルインデックスとは?評価項目と基準・評価する人・評価方法など
▶︎ADLの評価方法とは|介護・看護・医療で把握する目的・項目や書き方を徹底解説
デイサービスでの機能訓練を担う機能訓練指導員の職種には様々な職種があります。それぞれリハビリテーションの専門職や、痛みや苦痛の改善の専門職、人の健康を支える専門職などの特色があります。
これだけの職種が機能訓練をになっていくため、考え方や方法も異なります。また、現在はリハビリ特化型デイサービスが非常に増えたことから「マシントレーニング」を提供している事業者が多くなっていますが、身体機能面のアプローチだけでなく、自立支援のためになる機能訓練を目指していくことが推奨されています。
「筋力低下を予防しましょう」ということがコンセプトになっていることが多いです。
機能訓練指導員について知りたい方は、ぜひこちらの記事をご一読ください。
▶︎機能訓練指導員の仕事内容|必要な資格・加算による配置基準とは
デイサービスに通われている方は高齢者です。
高齢者は相対的な日々の活動力が落ちてくることや、病気や障害から、ロコモティブシンドローム(以下、ロコモ)やフレイルといった状態に陥りがちです。
例えば介護予防事業などでは、運動器の機能低下が自立生活の根底である歩行能力の低下の大きな要因となっているという考えに基づき、ロコモを予防するような運動などの取り組みを行うことが進められています。
ロコモやフレイルを予防することは健康長寿の秘訣ですので、適切な評価と運動プログラムの立案・実践が必要になります。
ここまで述べてきた通り、機能訓練という言葉から筋力トレーニングなどのような身体的部分に着目されてしまいますが、最終的に必要なことは生活機能の維持改善です。また、良い状態を保つような予防的な考え方も必要です。
「自立支援」とは「精神的かつ社会的にも安定した状態」をサポートしていくことです。そのために、デイサービスにおける機能訓練というのは非常に重要な位置付けにあります。
デイサービスにおける自立支援と、機能訓練の必要性について考えてみましたが、いかがでしたでしょうか。
自立支援について考えることは、決してデイサービスに限ったことではなく、介護・医療に携わる方全ての方が意識するべき部分です。
少しでもこの記事が参考になれば嬉しく思います。最後までお読みいただきありがとうございました。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。
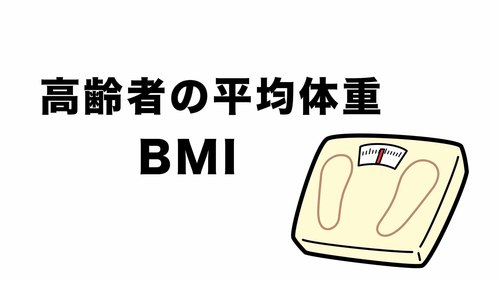
現場ノウハウ
2024/04/23

現場ノウハウ
2024/04/23

現場ノウハウ
2024/04/23

現場ノウハウ
2024/04/23
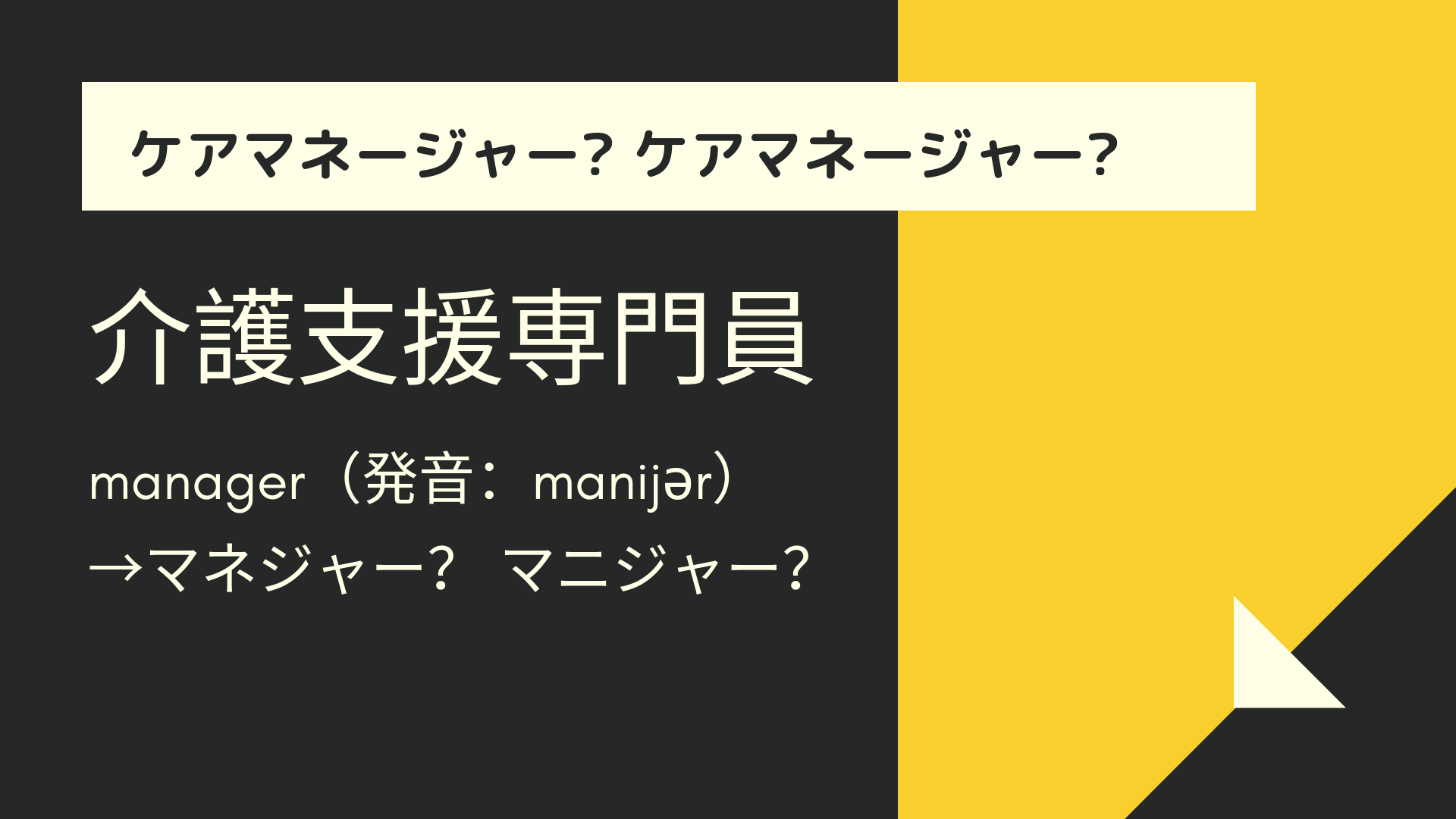
現場ノウハウ
2024/04/23

現場ノウハウ
2024/04/23