「介護×ICT」で現場はどう変わる?メリットと導入事例・今後の展望
運営ノウハウ
2024/04/18
運営ノウハウ
介護用品・福祉用具
更新日:2022/02/16
福祉用具の中でも歩行器にはどんな種類があるか知っていますか?歩行器は、歩行補助具とも呼ばれ、足腰が弱い高齢者や骨折・片麻痺など歩行障害のある方が使う道具の一つです。最近では色や形、種類も多種多様となりました。今回は、ご利用者様にとってどの歩行器が良いのか?なぜこの歩行器を使っているのか?など介護スタッフの基礎知識としてご紹介します。
→科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
→無料研修会「ついに始まる2024年度介護報酬改定 全貌を一気に解説!」
この記事の目次

介護現場でよく目にする「歩行器の目的」は、疾患や疾病によるバランスの不安定さをで軽減し「転倒リスクを減らす」ことです。
人は身体を支える面積(支持基底面)が広いほど身体動作は安定します。
そのため歩行器を使用し、移動時の基底面を広くすることでバランスを保ちます。
歩行器の種類は以下のものがあります。

固定型歩行器は、3つのポイントがあります。
移動スピードが極めて遅くなるため、屋外など移動範囲が広い場所での使用は不向きと言えます。
利用対象者としては、以下の2つを押さえておきましょう。
交互型歩行器は、左右のフレームが個々に動かせるものを言います。交互型歩行器の4つポイントをご説明します。
固定型歩行器に形状が似ていますが、歩行器を持ち上げることが無いので安定しやすくなります。しかし4動作歩行となるので、動作手順の理解が難しいことがあります。

前輪型歩行器は前輪にキャスターが付いたもの、四輪型は四脚にキャスターが付いたものを指します。
前輪型歩行器の3つポイント
四輪型歩行器の4つポイント

シルバーカーには椅子型やカゴ型、お盆・テーブル型などがあります。用途によって形状が様々ありますが、一般的なシルバーカーについてポイントをご説明します。
シルバーカーは低重量のため、段差や階段などで持ち上げることが難しくなります。用途や行き先によっては困難な場合がありますので、患者様の生活習慣や生活環境を確認し、適切なものをご提案しましょう。

ご紹介した歩行器を選ぶ際は、ご利用者様がどのような身体機能、環境にあるかを評価・質問して選定していきましょう。
いかがでしたか。今回は、福祉用具の選び方「歩行器編」についてご紹介しました。
それぞれの歩行器のポイントを理解することで、介護現場でもご利用者様の転倒リスクの可能性や身体の状態をより把握することができます。
今回の記事を参考に、ご利用者様の目標や目的にあった「歩行器」を選定して頂ければ幸いです。
可能であれば、自分1人で考えず、専門家でもある理学療法士や作業療法士などに相談して、ご利用者様の状態に合った歩行器や運動を選定してください。
「リハプラン」では、今回紹介した運動以外にも様々の道具を使用した運動を多数ご紹介しております。皆様の毎日が充実した、輝かしい日々につながるよう、ご協力が出来ればと思っています。何かご相談などがありましたら、連絡お待ちしています。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

運営ノウハウ
2024/04/18
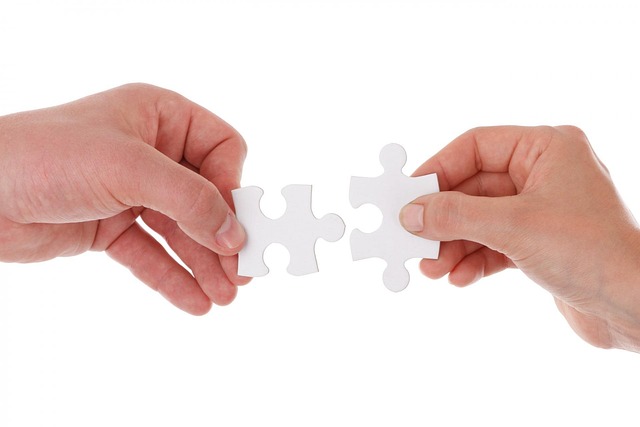
運営ノウハウ
2024/04/18

運営ノウハウ
2024/04/18

運営ノウハウ
2024/04/17

運営ノウハウ
2024/04/17

運営ノウハウ
2024/04/17