「介護×ICT」で現場はどう変わる?メリットと導入事例・今後の展望
運営ノウハウ
2024/04/18
運営ノウハウ
介護用品・福祉用具
更新日:2021/12/16
住宅改修の中でも設定させることが多いものに「手すり」があります。手すりは、階段やトイレなど日常生活の補助をしてくれたり怪我を防止、家族の介助を軽減するために有効です。そんな手すりの設置方法や手すりの選び方についてはご存知でしょうか? →忙しすぎるデイサービス業務は、機能訓練ソフト「リハプラン」が解決。
→科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
→無料研修会「ついに始まる2024年度介護報酬改定 全貌を一気に解説!」
この記事の目次

手すりは、段差やトイレ、浴室など日常生活の様々な場所で立ち上がりの補助や歩行の支えとしての役割があります。
しかし、不必要な部分に無駄に手すりを設置してしまうと通路の幅が狭くなったり、全く使わなかったりする場合も多くあります。ご利用者様の身体能力や生活を把握して適切な場所に設定することがとても重要です。

手すりを設置する効果には以下の5つの効果が期待できます。
⑴転倒や滑りなどの怪我を防ぐ
足元が滑って転倒しそうになる場合に支えとなります
⑵階段などの転落を防ぐ
階段の昇り降りの際に転落を防ぎます
⑶歩行の支えになる
歩く際のふらつきなどのバランスが不安定な場合に支えとなります
⑷立ち上がり動作が楽になる
玄関の上がり框やトイレ、浴室など立ち上がりを補助してくれます
⑸暗がりで誘導となる
視力が落ちたり、朝方の暗がりでつたい歩きを補助してくれます

「手すり」と言っても、用途や場所によって様々な形状や機能があります。一般的に使用される手すりについて以下にご紹介します。
1)縦手すり(I型手すり)
2)横手すり
3)L字手すり
4)波型手すり
5)可動型手すり
6)玄関手すり(タッチアップ手すり)

使用される方の身長や身体機能にもよりますが、手すりの高さを決める場合は以下のポイントを押さえておきましょう。
この3点を踏まえると床から「750~850mm」となることがほどんどです。
この高さを覚えておくのも良いでしょう。
1)腕をおろした手首の位置
2)大腿骨大転子(股関節の横に出ている骨)の位置
3)杖の高さ

ご利用者様の住宅改修で手すりを取り付ける前に必ずチェックしておくポイントをご紹介します。
⑴主な生活動線を確認
ご自宅での生活の中で必要な動線を確認しておきましょう。
⑵手すりを設置する位置や周辺のスペース、壁・床の状況を確認
手すりを設置する環境を調べてどのタイプの手すりであれば家族の邪魔にならないか、設置できるのか確認しておきましょう。
⑶使用者の身長や動作に合わせた手すりの形や長さ、太さを確認
身長によって高さが異なります。また、手すりの太さにより握りやすさを確認しておきましょう。
⑷手すりの材質を確認
屋外であれば雨なども考慮してステンレスやビニールコーティングなどを選択します。

玄関の上がり框や段差を登り終わる際、手すりの目的は身体を引き上げる補助となります。その為には以下のポイントを押さえておきましょう。
【玄関の場合】
靴を履き替える際に、バランスを失いやすくなるため支えとなります。また、上がり框を昇り降りする際に補助として役立ちます。
○縦手すり:ふらつきを補助、昇り降りを補助
○横手すり:立ち座りを補助
【階段の場合】
階段を降りる際の転倒防止に役立ちます。
○横手すり:転倒を防止
※高さは750mmが標準、階段を降りる際に利き腕に設置
玄関、階段の双方共に、以下の2点の設置方法を行うことで上半身重心が前方に移動するため昇降しやすくなる効果が期待できます。
1)肩の高さに縦手すりを設置
2)手すりの終わりを段差より100〜200mm前方に設置
手すりをつけよう!グリップグリップ「介護手すり取り付け位置・高さ 廊下・玄関・階段・トイレなどの室内」
平成29年4月12日アクセス

トイレや椅子からの立ち座り動作は身体を上下する動作になりますので、縦手すりやL型手すりが有効です。手すりの設置位置は以下のポイントを押さえておきましょう。
1)縦手すりは、便器の先端から200~300mm程度前方の位置
2)横手すりは、便座より230~300mm程度上の位置
【便所の場合】
手すりが便器に近すぎると前方に重心移動が出来ないため、腕の力に頼ることになり、手すりの効果を発揮できません。一方で、便器から手すりが遠くなると身体の重心移動を利用して立てるので、力学的には立ちやすくなります。
○縦手すり:入り口の出入りの安定性を補助、立ち上がりの補助
○横手すり:移乗時の補助、体の向きを変える際の補助
○L字手すり:立ち上がり、着座など上記を補助

手すりは立ち上がりや段差昇降時の支えとして便利な用具ですが、できることなら支えなく生活していきたいものです。そんな方々に、こちらの立ち上がりに必要なエクササイズをしてみませんか。
こちらの運動は、立ち上がり動作のための体幹ストレッチです。運動のポイントは、前方への重心移動を行うために頭と上半身を前方に倒すことです。

こちらの運動は立ち上がり動作のトレーニングです。
両手と上半身を前方への重心移動した後に、立ち上がりを行うタイミングがポイントです。目線をやや上方に挙げることを意識して行って下さい。
こちらの運動は、バランスディスクなども使用することができます。

縦手すりを使用した立ち上がりを行う際は、腕を縦にし(前腕中間位)引っ張りながら立ち上がることになります。
そのため、上腕二頭筋や特に腕撓骨筋と言われる二の腕の筋肉を使用します。上腕二頭筋や腕撓骨筋の筋力アップに効果が期待できます。
今回は、福祉用具の選び方「手すり編」についてご紹介しました。手すりの種類と設置ポイント、使用方法はご理解頂けたでしょうか。
今回ご紹介した「手すりの選び方」を参考に、ご利用者様の目標や目的にあった「手すり」や「運動」を指導をして頂ければ幸いです。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

運営ノウハウ
2024/04/18
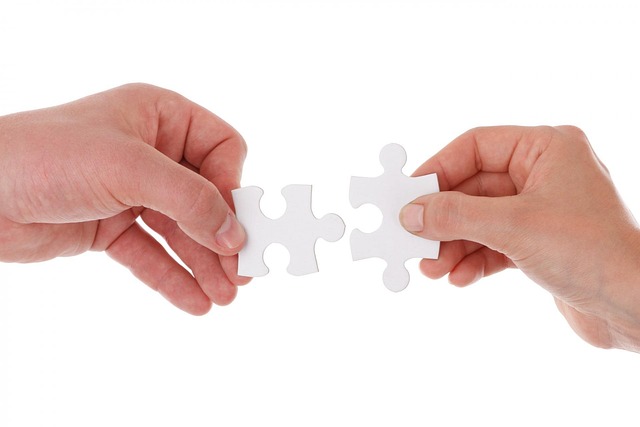
運営ノウハウ
2024/04/18

運営ノウハウ
2024/04/18

運営ノウハウ
2024/04/17

運営ノウハウ
2024/04/17

運営ノウハウ
2024/04/17