「介護×ICT」で現場はどう変わる?メリットと導入事例・今後の展望
運営ノウハウ
2024/04/18
運営ノウハウ
評価
更新日:2024/04/09
ICF(国際生活機能分類)とは、人間の「生活機能」と「障害」に関する状況を把握することを目的とした分類のことです。ICFで参加の項目を具体的にたくさん書き出すと、介護のリハビリテーション課題抽出や、ケアプランでのニーズの設定など課題(ニーズ)や介入点が抽出しやすくなるでしょう。この記事では、ICFの活動と参加の項目の違いや、どちらに区別するか迷った時の分類方法・考え方を解説しています。
→科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
→無料研修会「ついに始まる2024年度介護報酬改定 全貌を一気に解説!」
この記事の目次
▶科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!

ICFとは、「International Classification of Functioning, Disability and Health」の略称で、日本語では「国際生活機能分類」といいます。ICFは、元々WHO(世界保健機関)で1980年に制定された「ICIDH(国際障害分類)」の改訂版で、人間の「生活機能」と「障害」に関する状況を把握することを目的とした分類です。
これまで医療分野での障害の考え方は、ICIDH(国際障害分類)モデルでした。ICIDH分類では、身体機能の障害、生活機能(ADL・IADL)の障害、社会的不利(ハンディキャップ)で機能喪失や能力低下を分類するという障害重視の考え方であったのに対し、ICFでは環境因子や個人因子等の背景因子の視点を加えて、障害があっても「こうすれば出来る」というように生活すること・生きることの全体像を捉え、プラスの視点を持つように広い視点から総合的に理解することを目指しています。
| 【関連記事】 ICF(国際生活機能分類)とはどんな意味?簡単にICIDHとの違いを学ぶ 生活機能や障害の捉え方であるICFとICIDHの違いについてまとめて解説しています。 |
▶科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!

心身機能(body functions)とは、身体の生理的機能(心理的機能を含む)のことです。身体構造(body structures)とは、器官、肢体とその構成部分などの、身体の解剖学的部分のことです。心身機能、身体構造(body function & structure)の具体例としては、身長、体重、筋力、柔軟性、肢長、認知機能、麻痺などが挙げられ、体の働きや精神の働き、体や体の一部のの構造のことを指します。
機能障害(impairments)とは、ICIDH(国際障害分類)で分類するときに、著しい変異や喪失などの病気や怪我、心身機能の問題のことを指します。機能障害の具体例としては、下肢の筋力低下や右片麻痺などですが、ICFでは機能低下というネガティブな捉え方でなく、心身機能や身体構造という心身の特徴として考えるためICF分類ではあまり機能障害という表現はあまりしません。

▶科学的介護ソフト「Rehab Cloud」は2024年度の介護報酬改定に対応!
ICFの活動(activity)とは、個人による課題や行為の遂行のことです。ICFの「活動」は「個人レベル(生活レベル)」と表現され、個人として生活する上で、生きていくために役立つ様々な行為と定義されます。日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL)などの項目が含まれます。
具体的なICFの「活動」の項目の例は以下の通りです。
起居動作(寝返り・起き上がり・立ち上がりなど)、食事、整容(歯磨き・髭剃り・化粧など)、入浴(体洗・洗髪・浴槽移乗など)、更衣(ズボンや上着・下着の着脱など)、トイレ、車椅子または歩行(杖歩行や歩行器歩行など)、階段、移乗(トイレ移乗・ベッド移乗など)
電話を使用する、買い物、食事の準備、家事、洗濯、運転や交通機関の利用、自分の服薬管理、財産や金銭の取り扱い、仕事、交際、趣味などの生活行為まで含みます。
活動制限(activity limitations)とは、個人が活動を行う際の困難さのことで、ICFの活動項目が困難になった状態のことを指します。しかし、ICFではICIDH(国際障害分類)で分類するときとは異なり、制限というネガティブな表現でなく、活動や行為の状態そのものを個人因子や環境因子、健康状態、心身機能などとの相互作用モデルで考えていくため、ICF分類ではあまり活動制限という表現はしません。

ICFの参加(participation)とは、生活、人生場面(life situation)への関わりのことです。ICFの「参加」は「社会レベル(人生レベル)」と表現され、社会的な出来事に関与したり、役割を果たすことと定義されます。具体的なICFの参加には、主婦としての役割や、仕事の役割、地域での係、交友関係の中での役割などの社会参加や人生の過程での立場や存在価値、コミュニティに関与することなどが含まれます。
具体的なICFの参加(participation)の例は以下の通りです。
主婦として家事全般を行う、カラオケクラブに行く、自治会長として職務を行う、ゲートボールの集まりに行く、娘の結婚式に出席する、書道の展覧会に出品する、俳句のコンクールに応募する、家業の農家の手伝いをするなどが挙げられます。
参加制約(participation restrictions)とは、個人が生活、人生場面に関わる際に経験する問題で、ICIDH(国際障害分類)で分類するときのハンディキャップに近い意味合いですが、ICF分類ではあまり参加制約という表現はせず、どうしたら参加できるかという視点で個人因子や環境因子、健康状態、心身機能、活動状態などとの相互作用モデルで考えていきます。

ICFの活動と参加の違いは、その活動や行為が、個人の生活レベルであるか、社会や人生に関わるレベルであるかによって判断されます。
必ず活動にはこの項目が入るというものではなく、人によっては活動でも参加に関わっているケースもあります。

例えば、家事は、個人として生活する上でも重要なものですが、主婦として人生を送ってきた人で今後も家庭で主婦として役割を果たす場合には家庭というコミュニティで関与するものであり、参加の項目になり得ます。
ICFで分類するとき、参加の項目は「在宅復帰」という項目だけを挙げているケースも多くありますが、参加については柔軟に考えても大丈夫です。
買い物は「活動」の項目の例で挙げていますが、例えば八百屋さんが昔からの馴染で、そこで交流することが人生でとても重要な要素であるということもあり得ます。そのような場合には、活動には「〇〇m歩行できる」や「会話・コミュニケーションができる」が分類し、参加には「八百屋に買い物に行き、〇〇さんたちと談笑する」を分類するなどでも間違いではありません。
買い物に行けるいう活動能力としての点だけでなく、孤立したり交流の楽しみが失われたりしていないかという点に気付くための要素として、身体能力的に無理なことでも参加についても十分に聞き取りして、考えていく必要があります。
参加の項目は、人生での楽しみや、社会的に得られる承認や存在意義などを見出せるものなどQOLにも関わるもので、この項目しか活動や参加に分類してはいけないというルールはありません。
できるだけたくさん、具体的にその人らしい「参加」を書き出した方がその人の生活歴や人生、全体像が見えてきて、課題(ニーズ)や介入点が抽出しやすくなります。参加の項目は、個人因子や環境因子の項目とも重複する部分がありますが、重複するということは相互に関連性が深いと意味なので片方にしか書いてはいけないということもありません。
ぜひ、ICFを上手に活用して、リハビリテーションの課題抽出や、ケアプランでのニーズの設定など、QOLの向上に役立ててみてください。
| 【関連記事】 QOL(生活の質)とは?患者様が求める生活を支援するQOLの基礎知識 QOLとは、人間の「生活の質」を指しており、患者様やご高齢者が望む生活を支える上で重要な考え方です。 今回は、クオリティ・オブ・ライフと呼ばれるQOLの考え方や評価方法についてまとめて解説しています。 |
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

運営ノウハウ
2024/04/18
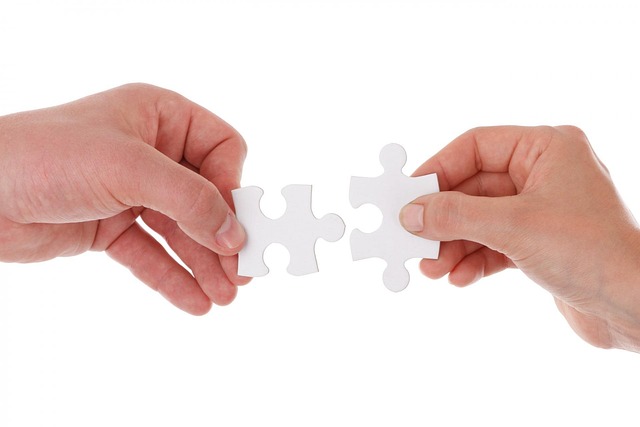
運営ノウハウ
2024/04/18

運営ノウハウ
2024/04/18

運営ノウハウ
2024/04/17

運営ノウハウ
2024/04/17

運営ノウハウ
2024/04/17