【保存版】デイサービスの生活相談員の仕事内容 業務に役立つ情報まとめ
現場ノウハウ
2024/04/25
現場ノウハウ
お役立ち情報
更新日:2024/04/07
「機能訓練」と「リハビリ」は似たような印象の言葉ですが、定義や前提条件に違いがあります。 介護現場のスタッフが間違った理解をしていると行政の運営(実地)指導や監査でご指摘を受けることになるため、注意が必要です。この記事では、機能訓練とリハビリの定義や基本方針の違い、実施者の違いなどについて、「通所介護」と「通所リハ」の視点からご紹介していきましょう。
この記事の目次
▶︎令和6年度の介護報酬改定では、科学的介護の推進がさらに加速します。LIFEの利用も必須になっていくことが予想されます。スムーズにLIFEに情報を提出されている各地の事業所の事例をご紹介します。
リハビリテーションと機能訓練の違いを、介護保険上の定義の違いから解説していきます。運営基準では以下のように示されています。
介護保険制度におけるリハビリと機能訓練の大きな違いとしては「医師の指示」にもとづいて訓練を行う必要があるかどうかです。
また、リハビリには定められている専門職種が訓練を行いますが、機能訓練では介護職員をはじめとしたその他職員でも実施が可能です。
リハビリと機能訓練には法律的な違いがあるわけではなく、医療現場・介護現場それぞれのシーンで言葉が分かれるケースが多いです。
参考:厚生労働省「リハビリテーションと機能訓練の機能分化と その在り方に関する調査研究」(2016年3月) (2023年6月4日確認)
機能訓練とリハビリの違いについては、「通所介護」と「通所リハビリ」の基本方針の違いについて理解しておくと、さらに理解が深まります。
基本方針・対象者・実践者の3つの違いから抑えていきましょう。
通所介護では利用者の心身機能だけでなく、取り巻く環境に対してもアプローチする必要があります。
一方で、通所リハビリでは心身機能の維持・改善を目的としたリハビリが中心となっています。
どちらも居宅要介護者が対象者ですが、通所リハビリでは医師が治療が必要と診断した場合のみサービスが提供されます。
つまり、通所リハビリの対象者は医師によるリハビリの指示を受けた方のみとなります。
通所介護では、上記の「機能訓練指導員」に当てはまる資格を取得している方であれば実施可能です。
一方で、通所リハビリは理学療法士をはじめとした、リハビリを専門とした資格を取得している方のみに限定されます。
参照:厚生労働省「リハビリテーションと機能訓練の機能分化と その在り方に関する調査研究」(2016年3月) (2023年6月4日確認)
ここでは通所介護で実施される内容についてご紹介します。
機能訓練ではどのようなことを行うのか、その具体的な内容についておさえておきましょう。
通所介護での機能訓練は、機能訓練指導員のもとで行われます。
機能訓練指導員とは先ほど説明した通り、以下のいずれかの資格を持っている方が該当します。
機能訓練で行われる内容としては、以下の通りです。
このように、利用者の心身機能を維持するための内容が実施されます。
身体を動かすための体操やレクリエーションなどのプログラムを中心に行われます。
通所リハビリで実施される「リハビリテーション」は、おもに3種類に分かれます。
ここではそれぞれの具体的な内容についてご紹介します。
理学療法とは、病気やケガなどが原因で身体に障害がある方に対して、基本的な動作能力の回復を図るためのリハビリです。
理学療法として行う内容としては、以下があげられます。
これらの内容を、「理学療法士」がサポートしながら行います。
作業療法士とは、病気や怪我などによって身体・精神に障害を持った方に対して応用的な動作、社会に適応できる能力の回復を図るためのリハビリです。
作業療法では手芸や工作、パソコンの操作など、応用的な動作の練習を中心に行うのが特徴です。
「理学療法=基本的な動作」「作業療法=応用的な動作」というイメージを持つとわかりやすいでしょう。
作業療法は「作業療法士」がサポートしながら行います。
言語聴覚療法とは、言葉や食事、聴覚などに関わる能力に障害を持つ方に対して、それらの機能の維持・向上を図るためのリハビリです。
障害を持った方に必要な検査を行ったうえで、以下のようなリハビリを提供します。
言語聴覚療法は「言語聴覚士」とともにリハビリを進めていきます。
介護保険制度における機能訓練とリハビリの違いとしては、「医師の指示」があるかどうかがポイントです。
通所リハビリで行われるのがリハビリで、通所介護で提供するサービスの一部が機能訓練と表現するとわかりやすいでしょう。
また、通所介護をはじめとした介護保険サービスは機能訓練で、医療保険サービスを提供する機関ではリハビリのケースが多いといえます。
これらの前提条件を踏まえたうえで、機能訓練とリハビリの違いについておさえておきましょう。
リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。
日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?
『科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!
ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。
リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

現場ノウハウ
2024/04/25

現場ノウハウ
2024/04/25

現場ノウハウ
2024/04/25
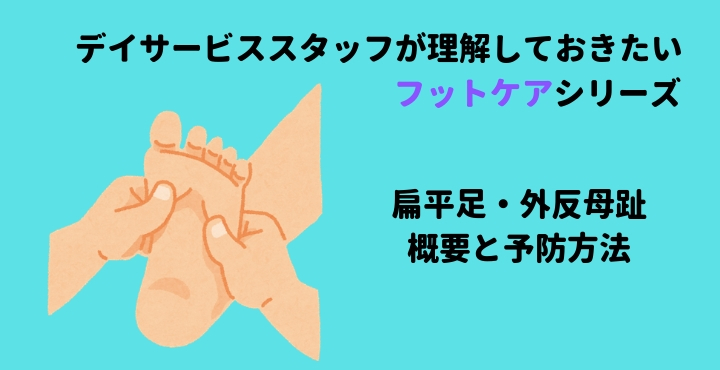
現場ノウハウ
2024/04/25
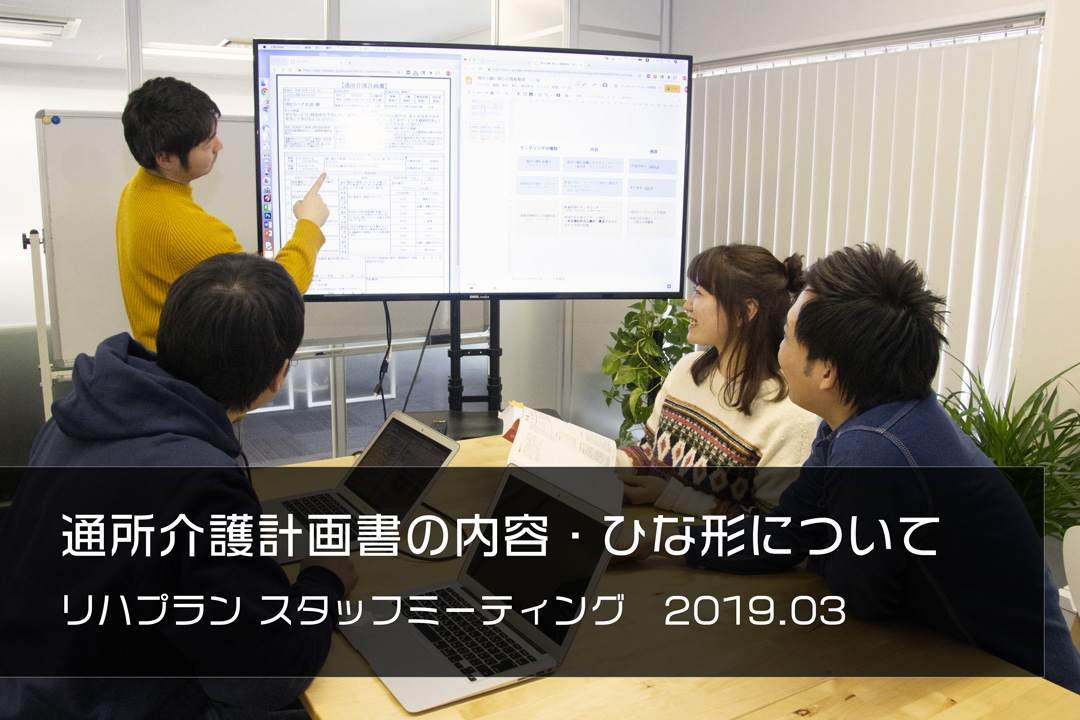
現場ノウハウ
2024/04/25

現場ノウハウ
2024/04/25